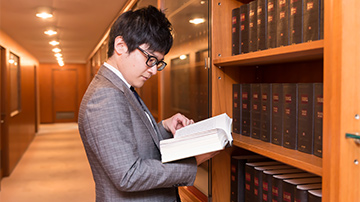最重要実務解説
贈与無効、死因贈与無効
2025.07.24
1 贈与、死因贈与について
⑴ 贈与とは
贈与とは、贈与者が自分の財産を無償で相手に与えることを伝え、相手が受け取ることを承諾することで成立する契約をいいます(民法549条)。
贈与の種類には、定期贈与(民法552条)、負担付贈与(民法553条)、死因贈与(民法554条)などがあり、それぞれの民法に定めがあります。
⑵ 死因贈与とは
死因贈与とは、贈与者の死亡により効力が生じる贈与をいいます(民法554条)。
贈与者が死亡したときに効力が生じる点で通常の贈与と異なり、「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」とされています(民法554条)。
また、死因贈与は、贈与者の死亡により効力が生じることから、課税は贈与税ではなく、相続税の枠組みで行われることになります。
⑶ 死因贈与と遺贈の比較
死因贈与とよく似たものとして、遺贈があります。
遺贈とは、遺言によって、財産を渡すことをいいます(民法964条)。
死因贈与と遺贈は、死亡によって効力が生じる点や無償行為である点でよく似ていますが、以下のような違いがあります。
ア 行為態様の差異
死因贈与は、贈与者の贈与の申込に対し、受贈者がそれを承諾するという、贈与者と受贈者との合意が必要です。
これに対して、遺贈は、財産を渡すという遺贈者の一方的な意思表示(単独行為)で成立します。
イ 要式性の有無
死因贈与は贈与の一類型であるため、方式に決まりはなく、口頭であっても有効に成立します。
一方、遺贈は、遺言によって行われる行為であるため、遺言の方式を満たしている必要があり(民法967条)、遺言の方式を満たしていないと無効になります。
ウ 不動産登記の登録免許税
死因贈与と遺贈では、相続人に対して行った場合の不動産登記の登録免許税に差異があります。
エ 年齢
死因贈与は贈与の一類型であるため、成人(18歳)に達している必要があり、遺贈は、遺言によって行われる行為であるため、15歳に達していれば行うことができます(民法961条)
以上を表にすると以下のとおりです。
| 死因贈与 | 遺贈 | |
|---|---|---|
| 行為態様 | 契約 | 単独行為 |
| 要式性 | 無 | 有(遺言の要式を満たすことが必要) |
| 不動産登記の登録免許税の税率 | 20/1000 |
相続人に遺贈する場合:4/1000 相続人以外に遺贈する場合:20/1000 |
| 年齢 | 18歳以上(ただし、法定代理人の同意があれば18歳未満でも可能) | 15歳以上 |
| 課税 | 相続税 | 相続税 |
⑷ 要式を満たさない遺言が死因贈与として効力が認められる可能性
遺言の方式を満たしておらず、遺贈としては無効とされてしまう場合でも、口頭でも足りるなど特に要式性が求められていない死因贈与としてはその効力が認められる場合があります。
この場合についての詳細は、「遺言無効のページ」のとおりです。
2 贈与、死因贈与の効力が否定される類型
贈与や死因贈与の効力が否定される場面は様々ですが、概ね以下の類型に分類できます。
⑴ 贈与契約や死因贈与契約の不存在
ア 契約書その他贈与、死因贈与の意思が記載された書面が偽造されていたような事例
贈与契約書や死因贈与契約書その他贈与や死因贈与を証する書面が存在するものの、それが贈与者本人が作成したものではない(偽造されたもの)であるとして、贈与や死因贈与の効力が否定される事例があります。
イ 契約書は存在しないものの死因贈与の主張がなされる事例
契約書などの直接的な書証が存在しない場合に、口頭での贈与者とのやりとりや契約書に至らないような贈与者のメモ書きなどを根拠に贈与や死因贈与がなされたという主張がなされ、その主張が排斥される事例があります。
⑵ 贈与契約や死因贈与契約の無効
贈与契約書や死因贈与契約書など贈与者本人が作成した書面が存在するものの、その贈与契約時点で、贈与者が、認知症、統合失調症などの事情により既に意思能力を有しなかったものとして、契約が無効とされる事例があります。
⑶ 贈与契約、死因贈与契約の錯誤、詐欺、強迫を理由とする取消(無効)
贈与や死因贈与の意思表示の過程に、錯誤(民法95条)、詐欺(民法96条)、強迫(民法97条)があったとして、取消や無効が主張される事例があります。
⑷ 死因贈与契約特有の取消
死因贈与に特有のものとして、死因贈与については、「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」(民法554条)とされている関係で、遺言の撤回に関する規定である民法1022条、民法1023条の準用を根拠に、死因贈与契約の取消が主張される事例があります。
⑸ 公序良俗違反による無効
愛人関係を維持するために契約が行われた事例や、業者が高齢者に身元保証サービスを提供する代わりに財産の大部分を死因贈与させていたような事例(暴利行為の事例)など、契約が公序良俗に反して無効である(民法90条)と主張される事例があります。
3 贈与、死因贈与の効力の争いに関する裁判実務
本項では、上記2の類型のうち、⑴、⑵、⑷の類型に関する裁判実務について説明します。
⑴ 贈与契約や死因贈与契約の存否の争いに関する裁判実務
ア 契約書その他贈与、死因贈与の意思が記載された書面が偽造されていたような事例
(ア)裁判実務上重要となる要素
(死因)贈与契約書などの偽造が争われる裁判例では次のような要素が重視して判断がなされています。
① 贈与者の署名・押印の有無
契約書に署名があるか、記名があるのみであるかは、その契約書が本人が作成したか(本人以外が偽造したか)を判定する上での一つの重要な要素です。
署名がある場合は、それが本人の筆跡であるかなどが検討されますが、筆跡鑑定の結果から直ちに結論を出すようなことはせず、作成時の状況その他の事情を総合的に検討して結論が出されています。
② 贈与者の印鑑の管理状況
贈与者の実印が贈与者以外の者が使用できる状況であったかどうかなどが検討されます。
契約書に実印の押印がある場合は、通常は本人が作成されたことが強く推認されますが、たとえば、贈与者の実印を預かっている者がいるような場合や実印が誰でも使用できるような管理状況にあった場合には、契約書に実印の押印があるからといって直ちにそれが本人が契約書を作成したことを意味しないという方向で推認力を弱める形で作用します。
③ 贈与者と受贈者の関係性、動機
贈与者が受贈者に(死因)贈与を行う関係性や動機があるかが検討されます。
特に、贈与は、受贈者に無償で財産を渡す行為であるため、そのような行為を行う関係性にあるかどうか、贈与者に贈与を行う動機があるかが重要な判断要素となります。
④ (死因)贈与契約書等の作成前後の事実関係
贈与契約書が作成されるまでの経緯、たとえば、弁護士や税理士への相談を行うなど贈与を行うにあたっての事前の検討を行っていた経緯があるか、贈与契約書が作成されたとされる時期以降の贈与者の受贈者の行動が、贈与契約書が作成されたという事実と整合するか(それと矛盾する行動をとっていないか)などが重要な判断要素となります。
(イ)裁判例
(死因)贈与契約書の成立の真正(本人が作成したか、偽造されたか)が争われた裁判例は多数ありますが、たとえば、以下のようなものがあります。
① 文書の成立の真正を否定した裁判例
・東京地判令和4年5月18日
負担付死因贈与契約書について、受贈者が贈与者の後見人であり、贈与者の印鑑を管理していたことから、贈与者の押印がなされているとしても、贈与者の意思に基づいて顕出されたと事実上推定することはできないとしつつ、贈与者名義の署名はあるものの、作成経過や体裁等に照らすと贈与者の自署によるものであるとの証明はできないとして死因贈与契約の成立を否定しました。
・東京地判平成31年2月28日
亡夫が保有する株式の全てを妻に贈与する内容の死因贈与契約書について、亡夫の生前と死後の実印の保管状況から妻が亡夫の実印を押印することは極めて容易であったとして、贈与者の押印がなされているとしても、贈与者の意思に基づいて顕出されたと事実上推定することはできないとしつつ、贈与の動機・経緯、発見経緯などに不自然な点があることなどを理由に死因贈与契約書の成立の真正を否定しました。
② 文書の成立の真正を肯定した裁判例
・東京地判令和6年3月26日
成立の真正が争われた株式譲渡契約書について、贈与者と受贈者が同居していたことから贈与者の印章による印影があることから直ちに贈与者の意思に基づいて顕出されたものと認めることはできないとしつつも、筆跡が贈与者が自署した他の書類の筆跡と類似していることや贈与に至る経緯などから当事者の供述の信用性を検討し、文書の成立の真正を認めています。
・東京地判令和5年7月27日
贈与契約書の成立の真正について、贈与者の管理する印章による印影があることから文書の成立の真正が推定されるとし、冒用がされた旨の贈与者の主張については、印章の保管状況に関する的確な証拠や、受贈者が冒用したことをうかがわせる証拠がないとして、が争われた事例で、印章が、受贈者が出入りしていた事務所内で保管されていたとは認められず、受贈者に印章の冒用の機会があったとはいえないとして、文書の成立の真正を認めています。
・東京地判令和3年8月5日
押印のみで署名はなく、本文はすべてワープロで作成されていた死因贈与契約書の成立の真正について、贈与者の実印による印影があることから文書の成立の真正が推定されるとしつつ、受贈者が贈与者に対し継続的に金銭援助をしており、死因贈与契約の締結を条件に金銭援助をしていたと認められるなどの事情から、推定が覆されるものではないとして、文書の成立の真正を認めています。
イ 死因贈与契約書は存在しないものの死因贈与の主張がなされる事例
(ア)裁判実務上重要となる事情
死因贈与契約書は存在しない状況下で、口頭でのやりとりや贈与者の意向を記したメモ、預かった物品などを根拠に死因贈与がなされたという主張がされる事案があります。
たとえば、銀行の情報を書いたメモとともに通帳と銀行印を預かったことなどを根拠に贈与がなされたと主張される場合などがあります。
こうした事案の裁判例では、次のような要素を重視して判断がなされています。
① 贈与者と受贈者の関係性
受贈者が贈与者の生活の面倒を見ている、受贈者以外の者に財産を渡したいと考える者の候補者がいない(相続人がいない、身寄りがない)などの事情は、贈与者の贈与意思を肯定する方向での重要な判断要素となります。
② 死因贈与の意思を推認させる客観的事情の有無
たとえば、自分が持っている財産は全て使ってほしいと受贈者に口頭で告げるとともに、銀行に関する情報を記載したメモ、通帳や銀行印なども合わせて交付しているなどの客観的事実の裏付けが伴う場合には、贈与意思を肯定する方向で作用します。
③ 死因贈与契約書や遺言などが作成されなかった事情の有無
贈与契約書や遺言などを作成することが通常と思われる状況下でそうした書面が作成されていなければ、贈与意思を否定する方向で作用しますが、当事者の関係性や贈与者の体調などからそのような書面が作成されていないことにも合理性がある場合には、直ちに贈与意思が否定されることにはなりません。
(イ)裁判例
このように死因贈与の主張がなされた裁判例は多数ありますが、たとえば、以下のようなものがあります。
① 死因贈与の成立を否定した裁判例
・東京高判平成21年8月6日
口頭による死因贈与の主張がなされた事案において、受贈者のほかに相続人がいるにもかかわらず死因贈与の合意を証する書面がないこと、死亡した贈与者の遺産目録に対象財産が計上されていたことなどから、死因贈与の成立を否定しています。
② 死因贈与の成立を肯定した裁判例
・東京地判令和4年12月14日
土地の賃貸借契約書の特約条項に、贈与者が死亡したときに受贈者に遺産として相続することを約する記載があった事例で死因贈与の成立を肯定しています(ただし、直接の争点は本体の契約の性質とその占有権限の相続性。)。
・東京地判平成27年8月13日
身寄りのない贈与者が身の回りの世話をしていた受贈者に銀行名やその概要等を記載したメモとともに通帳などを交付していた事例で、死因贈与の成立を肯定しています。
⑵ 贈与者の意思能力の存否の争いに関する裁判実務
ア 裁判実務上重要となる要素
贈与や死因贈与は、高齢者や病気などによって死期の近づいた者によってなされる(なされたと主張される)ことが多く、そのため、贈与者に意思能力があったか、すなわち、自己の行為の法的な結果を認識・判断できる能力を有していたか、が争われることが少なくありません。
意思能力の有無は、贈与や死因贈与の場合に限られず、売買契約や連帯保証契約など様々な契約の場面で問題となるものであり、裁判例の集積があります。
また、死因贈与は、死亡によって効力が生じる点や無償行為である点で、遺贈とよく似ており、死因贈与がなされる状況は、その様式の点を除けば、遺言がなされる場合と非常によく似ているため、遺言能力の有無に関する判断要素「遺言無効のページ」も参考になります。
意思能力の有無は、画一的・形式的な基準で決まるものではなく、個々の具体的な事実関係に即して総合的に判断されるものですが、過去の裁判例をふまえると、贈与者の意思能力の有無の判断にあたっては、裁判実務上、以下のような要素が重要と考えられます。
① 贈与者の心身の状況
高齢であることや、統合失調症や認知症など知的能力面に障害を生じる病気に罹患していることは一つの重要な要素ですが、それが実際にどの程度意思能力に影響を与えているかが個別具体的に検討されます。
たとえば、贈与者が認知症に罹患していると診断されている場合であっても、直ちに結論が導かれるものではなく、個別具体的に認知症の程度やその法律行為時点の具体的な理解力や判断能力が検討され、争点となっている法律行為の難易度との関係で、十分な判断能力を有していたかどうかが検討されます。
また、認知症などの知的能力面に障害が生じる病気に罹患している場合、その症状が、一時的なものであり正常な時もあるのか、恒常的な症状なのか、あるいは、症状が時間の経過とともに悪化していくものなのかなどが検討されます。
一時的なものであれば、法律行為がなされた時点では、正常な判断能力を有していたかどうかが他の周辺事情などとあわせて検討され意思能力の有無を判断されます。
証拠方法に関しては、医師による診断書や鑑定書が存在する場合には、それが重視される傾向にあります。
もっとも、その医師が直接診断していた主治医であるか、認知症に関する専門的知識を有する医師であるか、診断書や鑑定書に相応の根拠があるかなどが詳細に検討され、信用性の低い診断書や鑑定書については排斥され、要介護認定の調査票や贈与者と日常的に接触していた者の証言の方が重視される場合もあります。
② 契約書等の作成時の様子
契約書を作成する場面において、公証人、弁護士、司法書士などが立ち会っている場合には、それらの者の供述が参考にされますが、医学的見地からの知見とその内容が対立する場合もあり、その場合には、個別具体的な事実関係に即して、いずれが信用できるかが検討されます。
③ 契約内容の複雑性
意思能力の欠缺に関する裁判例の一般的な傾向としては、契約内容が単純であればある程度理解力や判断力が低下している事情があってもその判断に必要な程度の意思能力は備えているとして意思能力が肯定される方向に作用し、複雑であるほど高度の理解力が要求され、意思能力が否定される傾向にあります。
これを贈与契約や死因贈与契約についてみた場合、財産を特定人に無償で渡すという単純な内容であると評価される場合もありますが、他方で、贈与行為単独で評価するのではなく、それによって失う経済的価値の重要性や、当該財産を贈与することによって財産を受け取ることのできない他の相続人に与える影響など、当該贈与や死因贈与によって生じる様々な結果についても十分に理解できる能力を要するという立場で、相当程度の理解力や判断力が要求され、それを有していなければ意思能力を欠くと判断される場合もあります。
④ 契約内容の合理性、動機
贈与者にとって贈与や死因贈与を行う動機がない場合や、贈与することによって単に重要な財産を失うという不合理な結果しかもたらさない(見合うメリットが贈与者にない)など契約内容が不合理な場合、正常な事理弁識能力を有していれば、そのような不合理な内容の契約をするはずがないという方向で、意思能力が否定される方向に作用します。
⑤ 贈与契約書等が作成される前後の事実関係
当該贈与に向けた行動を贈与者がとっていたか、当該契約を行った後の贈与者の行動が当該贈与を行ったことと整合するかが検討されます。
たとえば贈与や死因贈与を実行するために贈与者本人が税理士や弁護士に相談していたなどの事情や、死因贈与契約の締結後、贈与者が長男から長年にわたって生活支援や療養看護を受けた場合などが一例です。
⑥ 贈与者と受贈者の関係性<
贈与や死因贈与を受ける者の属性も重要な要素の一つです。
同居の長男に自宅を贈与するような場合は上記④のように動機や行為の合理性が認められ、意思能力が肯定される方向に作用します。
他方、相続人以外の者に贈与する場合や、受贈者以外に相続人がおり、当該贈与によって他の相続人の権利が大きく損なわれるような場合には、意思能力の有無についてより慎重に判断されます。
イ 裁判例
贈与や死因贈与について、贈与者の意思能力が争われた近時の裁判例には、たとえば以下のものがあります。
① 贈与者の意思能力を否定した裁判例
・東京地判令和4年2月8日
著名な画家の妻(亡妻)が地方公共団体に対して死亡を停止期限として贈与する内容の寄附申出書の作成時点における亡妻の意思能力の有無が問題となった事案において、対象財産の所有権を特段の対価なく喪失することになる意思表示は、慎重な検討を要する重要な財産の処分行為であって、その判断の難易度は相応に高いものであったとし、要介護認定の調査票の記載や寄附申出書が作成されるまでの経過などを検討し、意思能力を欠いていたと判断しています。
・仙台高判令和3年1月27日
アルツハイマー型認知症に罹患していた97歳の女性が夫の相続にかかる自己の相続分を長女に無償譲渡した契約について、弁護士2名の立会の下に相続分譲渡証書が作成されたという事案において、アルツハイマー型認知症の専門家である鑑定人医師の鑑定書の内容を重視し、相続分を無償譲渡するという意思表示のために必要とされる意思能力はなかったと判断しています。
・東京地判平成29年10月30日
89歳であった贈与者が姪である受贈者に1500万円を贈与する契約について、認知症の専門医の意見書の信用性を肯定し、贈与者が当時アルツハイマー型認知症に罹患し、慢性進行性の認知機能の低下をきたしていたと認定し、1500万円の贈与を、多額かつ片務の契約であり、日常行われる食料品や日用品の購入行為とは明らかに意味合いが異なるとした上で、贈与がなされた経緯、贈与の背景や合理性を検討し、贈与の際、意思能力はなかったと判断しています。
・東京地判平成25年9月26日
贈与者本人による署名捺印がなされている贈与契約書が存在する事案において、直接診察した医師による鑑定結果の信用性を肯定し、事理弁識能力は、少なくとも、そのほとんどが既に精神上の障害によって失われた状態にあったとしています。なお、贈与が同居の孫に贈与するという内容でその理解は容易であるという受贈者の主張に対しては、所有する大半の土地を相続人ではない孫に与えるということは、他の相続人に対する愛情との兼ね合いで相当に大きな決断であるはずであるとし、「直系だから当然」と評価することは困難であるとしています。
② 贈与者の意思能力を肯定した裁判例
・東京地判令和3年8月18日
亡夫の相続にかかる自己の相続分全部を子に贈与する内容の旨の契約が公正証書によってなされている事案について、贈与契約の7、8か月前の長谷川式認知症スケールやMMSEの結果はあまりよくなく、主治医が贈与契約締結時において「後見」相当であったと推認できる旨の意見を述べているという事情の下に、介護認定の際に主治医の意見が排斥され、一定の意思決定ができ、それを伝達できるものとして日常生活自立度についてはⅡbの評価、要介護1の認定にとどまっていたことや、公証人や贈与者とやりとりをした複数の者において判断能力に疑問があるとされていないことなどから、贈与者の判断能力がおよそ財産契約を結ぶのに適しない状態であったとはいえないと判断し、贈与契約の内容を、亡夫の相続に関し贈与者の自己の相続分全部を長男に贈与する単純な内容であるとした上で、贈与を行う動機、合理性を検討し、意思能力を欠いていた認めることはできないと判断しています。
・東京地判平成29年12月21日
贈与者の姪に対する1500万円を贈与する内容の死因贈与契約について、要介護認定の主治医意見書の内容や日々接していた介護の専門家の証言、死因贈与契約直前の贈与者の行動などから、贈与者が死因贈与契約当時、意思無能力であったとは認められないとしています。なお、自己の財産を適切に管理・処分できない状態であったとの判断が示されている別の医師の意見書については、その主たる根拠が死因贈与契約が行われた時より約4年後に撮影された頭部CTスキャン画像と約5年後に行われた長谷川式簡易知能評価スケールの成績であることなどから正確性に限界があるとしています。
・東京地判平成22年7月13日
長男が贈与者の生存中生活支援、医療管理、療養看護を行うことを負担として贈与者が長男に対して死因贈与を行う内容の負担付死因贈与について、贈与者に通常人には見られないような言動があったことが認められ、贈与者が入院中に診察していた医師が作成した診療情報提供書にも診断名に認知症との記載が存在するとしつつも、会話が成り立つときもあれば、話を理解することができないときもあるという波のある状態であったという、当該医師の供述から、贈与者が常に意思能力のない状態であったとは認められないとし、公証人が意思能力に問題がないことを確認した上で作成にとりかかったこと、贈与者が対象物件の住居表示と登記簿上の記載の相違を指摘したり、押印する印鑑が実印かどうかを気にしていたことなどから、贈与契約当時、意思能力がなかったと認めることはできないと判断しています。
⑶ 遺贈の規定の準用による死因贈与契約の取消の有無の争いに関する裁判実務
ア 死因贈与契約の取消に関する考え方
死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する(民法554条)とされています。
そして、遺贈に関する規定の中には、いつでも撤回できるとする規定(民法1022条)や、前の遺言の内容と後の遺言や後の生前処分その他の法律行為が抵触する場合には抵触する部分について撤回したものとみなすという規定があり(民法1023条)、これらの規定がどのような場合でも死因贈与にも準用され、自由に取消できるとすると、負担付死因贈与において受贈者がその負担をすでに履行した受贈者にとって不当な結論になってしまうことから、どのような場合に、こうした遺贈の規定が準用されるか(準用が制限されるか)が一つの論点となります。
この点については、最高裁判例は、死因贈与の取消について、遺言の取消に関する民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されるという立場をとりつつ(最判昭和47年5月25日)、負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし負担の履行状況にもかかわらず負担付死因贈与契約の全部又は一部の取消をすることがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、遺言の取消に関する民法1022条、1023条の各規定を準用するのは相当でないという立場(最判昭和57年4月30日)をとっています。
また、裁判上の和解で死因贈与契約がなされた事案において、その和解条項の内容等もふまえてその死因贈与を贈与者に自由に取り消すことができないと判示している最高裁判例があります(最判昭和58年1月24日)。
イ 裁判例
① 負担付死因贈与の取消を認めた裁判例
・東京地判24年7月27日
贈与者が受贈者に対して830万円の債務を負っているという事実関係のもとになされた1億円超の不動産を贈与する死因贈与契約について、後に贈与者が婚姻し、子ができた後に作成された遺言による死因贈与契約の取消を肯定しています。
・東京地判平成7年10月25日
贈与者の生存中の介護が負担の内容となっていた負担付死因贈与について、受贈者が5年間の介護を行った後、それ以降は別の者が介護を行うようになった(その別の者による介護が今後も続くことが予定される)事案において、死因贈与契約の取消を肯定しています。
② 負担付死因贈与の取消を否定した裁判例
・東京地判平成5年5月7日
受贈者が贈与者に毎月50万円を贈与し、贈与者が死亡したときに土地を贈与する内容の死因贈与契約について、取消の意思表示がなされた時点ですでに土地の評価額と比べて少なくない額の支払が履行されていたことなどの事情から負担付死因贈与契約を取り消すことができないとしています。