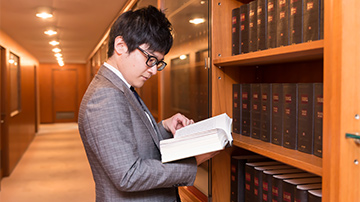最重要実務解説
遺留分侵害額請求
2025.07.24
1 遺留分侵害額請求とは
1 遺留分とは何か
遺留分とは、相続財産のうち、相続人が受け取ることを保障されている割合のことをいいます。例えば、相続人以外の第三者に全ての財産を渡す内容の遺言がある場合でも、相続人は遺留分を受け取ることができるので、いわば最低限度の相続分といえます。
2 遺留分侵害額請求権とは何か
遺言や生前贈与によって、相続人が受け取る相続財産の割合が遺留分を下回る場合、その相続人は受遺者(遺言により財産を受け取った人)や受贈者(生前贈与を受けた人)に対して、不足分を金銭で請求することができます。この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
この権利はあくまでも任意のものであり、行使するかどうかは相続人の自由です。
2 遺留分侵害額の計算方法
1 遺留分権利者
遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。
相続人のうち、配偶者、子(及びその代襲相続人)、直系尊属(親や祖父母)には遺留分が認められます。一方で、相続人である兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪には、遺留分は認められていません(民法第1042条第1項柱書)。
2 遺留分割合
⑴ 総体的遺留分
総体的遺留分とは、相続財産全体に対して、遺留分権利者全体に保障される割合のことをいいます。この割合は、相続人の構成によって異なります。相続人が直系尊属のみである場合は相続財産の3分の1(民法第1042条第1項第1号)、それ以外の場合は2分の1が遺留分として保障されます(同条第2号)。
⑵ 個別的遺留分
個別的遺留分とは、各遺留分権利者に対して保障される具体的な遺留分割合を指します。相続人が複数いる場合には、総体的遺留分に各人の法定相続分を乗じることで、個別的遺留分を算定することができます(民法第1042条第2項)。
⑶ 相続人の構成ごとに各相続人の個別的遺留分を算定すると、下記のとおりとなります。
| 相続人の構成 | 総体的遺留分 | 法定相続分 | 個別的遺留分 |
|---|---|---|---|
| 子1人のみ | 1/2 | 子:1/1 | 子:1/2 |
| 子2人 | 1/2 | 子:1/2ずつ | 子:1/4ずつ |
| 配偶者と子1人 | 1/2 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
配偶者:1/4 子:1/4 |
| 配偶者と子2人 | 1/2 | 配偶者:1/2 子:1/4ずつ |
配偶者:1/4 子:1/8ずつ |
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/1 | 配偶者:1/2 |
| 配偶者と直系尊属(父母など) | 1/2 | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
配偶者:1/3 尊属:1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者:2/3 兄弟姉妹:1/3 |
配偶者:1/3 兄弟姉妹:なし |
| 直系尊属のみ | 1/3 | 父:1/2 母:1/2 |
父:1/6 母:1/6 |
| 兄弟姉妹のみ | なし(対象外) | 兄弟姉妹:1/1 | なし |
3 遺留分算定の基礎となる財産の範囲
⑴ 遺留分を算定するための財産の価額は、
「相続開始時における被相続人の積極財産の価額」
+「相続人に対する生前贈与(特別受益)の額」(10年以内)
+「第三者に対する生前贈与の額」(1年以内)
‐「相続債務の額」
で計算します(民法第1044条)。
ただし、「遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与」については、1年前の日より前になされたものであっても、上記財産の価額に算入されます(後述)。
⑵ 生前贈与の諸問題
ア 「贈与」の意義
民法が規定する贈与契約に限らず、すべての無償処分を意味します。具体的には、寄付、信託の設定、無償での債務免除、無償での担保供与などが含まれると解されています。
イ 贈与の時期
遺留分算定の基礎となる財産に算入されるのは、原則として、相続人に対する生前贈与は相続開始前の10年間(3項)、第三者に対する生前贈与は相続開始前の1年間(1項)にされたものに限られます。
停止条件付贈与の場合、贈与契約の時期と贈与契約の効果が発生する時期が一致しないため、贈与の時期を「契約時」と考えるか、「効力発生時」と考えるか、という問題が生じます。
この点、仙台高裁秋田支部昭和36年9月25日判決下民12巻9号2373頁は、次のとおり判示し、「契約時」を基準とすることを明らかにしました。
「いわゆる相続開始前の一年前にした贈与にあたるかどうかは、停止条件附で贈与の意思表示がされた場合であると否とを問わず、贈与の意思表示がされた時を標準として判断すべく、その意思表示の時期が相続開始の時より一年前であるときは、相続開始前の一年前にした贈与であると解するのが相当である。」
ウ 「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた」贈与
民法第1044条第1項は、相続開始前の1年間に行われた生前贈与が遺留分算定の基礎となる財産に含まれることだけでなく、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」行われた贈与については、相続開始前の1年前の日より前に行われたものであっても遺留分算定の基礎に含まれることを定めています。
「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」とは、遺留分権利者に損害を加えるべき事実を認識していることで足り、加害の意図を持っていることや、誰が遺留分権利者であるかを知っている必要はありません。
この点に関し、以下のような事例があります。
(ア)肯定例
① 父が全財産に当たる3つの不動産を自らの弟に生前贈与していたため、唯一の相続人である娘が弟に対し遺留分減殺請求をしたところ、贈与の当時、当事者である父と弟の双方が、不動産を全て弟に贈与すれば父には財産の残りがなくなることを知っていたばかりでなく、父の健康状態からすれば死亡の時までに同人の財産が増加しないであろうということを予想していた、と判断された事例(前橋地判昭和32年6月6日下民8巻6号1070頁)。
② 養父が全財産に当たる2つの不動産を順次甥に生前贈与したことに対して、養子が遺留分減殺請求をしたところ、裁判所が、養父及び甥が当該贈与によって養父の財産が失われることを知っていただけでなく、養父の財産がその死亡時までに増加することもないと予見していたと判断した上で、損害を加えることを知ってした贈与とは、相続人が2分の1の遺留分を有する本件においては、贈与当事者が贈与財産の価額が残存財産の価額を超えていることを認識し、かつ被相続人の財産が相続開始時までに増加しないことを予見していれば足り、相続開始時における遺留分権利者の有無やその同一性までを予見している必要はない、と判断した事例(仙台高判秋田支部昭和36年9月25日)。
(イ)否定例
③ 原告らが、被相続人が生前に被告へ贈与した不動産が遺留分を侵害するとして遺留分減殺請求を行った事案において、裁判所が、「損害を加えることを知ってなした贈与」であるか否かは、贈与財産の全財産に対する割合のみならず、贈与の時期、贈与者の年齢、健康状態、職業等から将来財産が増加する可能性が少ないことを認識してなされたかによって判断すべきとした上で、被相続人が健康で収入が十分ある時に行われた贈与は、将来の財産減少を予見していたとは認められないことから、「遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与」とは評価できず、また、被相続人が健康を崩し収入が低くなった時に行われた贈与は、贈与財産と遺産全体との比較において遺留分の侵害は認められないとして、原告らの請求を棄却した事例(東京地判昭和51年10月22日・判時第852号80頁)。
エ 負担付贈与
負担付贈与がされた場合に遺留分を算定するための財産の価額に加算する贈与の額は、贈与の目的となる財産の価額から負担の価額を控除した額となります(民法第1045条第1項)。
オ 不相当な対価をもってした有償行為
不相当な対価でなされた有償行為は、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り」、対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされます(同条2項)。
カ 持戻し免除の意思表示がなされた場合の扱い
「持戻し免除の意思表示」とは、遺産分割において、特別受益を受けた相続人がいても、その特別受益を相続財産に加算しない(持戻さない)、という被相続人の意思表示のことを指します(民法第903条第3項)。このような意思表示があった場合、対象となる生前贈与が遺留分を算定するための基礎となる財産に含まれなくなるのでしょうか。
この点、多額の贈与を行い、持戻しを免除することで、遺留分を算定するための基礎財産の価額を減少させることが可能であれば、他の相続人の遺留分を恣意的に縮小できることになります。これでは、最低限度の相続分を保障する遺留分制度の本来の目的が損なわれるおそれがあります。したがって、持戻し免除の意思表示があった場合でも、その生前贈与は遺留分算定の基礎財産に算入されます。
最判平成24年1月26日判時2148号61頁は、「上記の遺留分制度の趣旨(※被相続人の財産処分の自由を制限し、相続人に対して一定割合の財産取得を保障すること)等に鑑みれば、被相続人が、特別受益に当たる贈与につき、当該贈与に係る財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(※持戻し免除の意思表示)をしていた場合であっても、上記価額は遺留分算定の基礎となる財産額に算入されるものと解される。」と判示しています。
キ 生命保険金の持戻し
(ア)生命保険金の受取人が相続人である場合、保険金請求権は相続財産になる余地はなく、受取人の固有の権利であるとするのが通説・判例です(大判昭和11年5月13日民集15号877頁、最判昭和40年2月2日判時404号52頁、最決平成16年10月29日判時1884号41頁など)。したがって、原則として、遺留分算定の基礎となる財産の価額を算定するに際し、生命保険金が持戻されることはありません。
もっとも、「特段の事情」がある場合は例外です。最決平成16年10月29日判時1884号41頁は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」述べています。ただし、この最決では、生命保険金の持戻しは否定されました。
(イ)持ち戻し肯定例
① 東京地判令和6年5月10日(令和4年(ワ)第10651号)
(裁判例において考慮された事情)
・生命保険金の金額:2億円
・相続財産の金額:約4億7500万円
・生命保険金の相続財産に対する比率:約42%
・当該生命保険契約は貯蓄性が高く投資信託に似た性質を有すること
② 東京地判令和5年12月1日
(裁判例において考慮された事情)
・生命保険金の金額:1億5000万円
・相続財産の金額:約9億円
・生命保険金の相続財産に対する比率:約15%
・相続に近接した時期(遺言作成後、相続開始の3年半前)に保険に加入していること
・1億5000万円という金額がそれ自体多額であること
・保険料一括払いの保険であり、投資信託と類似点が多いこと
・遺言で原告に相続させるとされたのは金融資産の5分の1のみであること
③ 東京地判平成31年2月7日
(裁判例において考慮された事情)
・生命保険金の金額:5000万円
・相続財産の金額:約1億1000万円
・生命保険金の相続財産に対する比率:約45%
・生命保険金以外に被告が約2億円の特別受益を受けていること
(ウ)持戻し否定例
① 東京地判令和6年5月10日(令和2年(ワ)第4947号)
(裁判例において考慮された事情)
・生命保険金の金額:9900万円
・相続財産の金額:約6億8000万円
・生命保険金の相続財産に対する比率:約14%
・保険契約締結時点で、被告が被相続人と同居して、被相続人の介護等にも貢献していたこと
② 東京地方判令和6年3月21日
裁判例において考慮された事情)
・生命保険金の金額:7100万4717円
・相続財産の金額:約3億1000万円
・生命保険金の相続財産に対する比率:約23%
・被相続人の生活の介助に対する原告の貢献度合いが特に高いとは認め難いこと
③ 広島高決令和4年2月25日(※遺産分割の事案)
(裁判例において考慮された事情)
・生命保険金の金額:2000万円
・相続財産の金額:772万3699円
・生命保険金の相続財産に対する比率:約2.7倍
・被相続人と相手方(受取人)は、婚姻期間約20年、同居期間約30年の夫婦であること
・2000万円という金額は一般的な夫婦間の保険金の額として高額とはいえないこと
・相手方は専業主婦で、被相続人の収入以外に収入を得る手段がなかったこと
・相手方との婚姻を機に死亡保険金の受取人を相手方に変更していること
・他の相続人は、被相続人と長年別居し生計を別にする母親であること
⑶ 寄与分の扱い
遺留分侵害額請求を受けた者が、寄与分を主張して、遺留分侵害額請求額の減額を主張することはできません。
この点について述べた東京高判平成3年7月30日判時1400号26頁では、以下のとおり判示し、寄与分の考慮を否定しています。
「被控訴人は、抗弁1において、被相続人の相続財産である本件不動産につき六割の寄与分があるので、具体的遺留分の計算において、これを考慮すべき旨主張する。
しかしながら、寄与分は、共同相続人間の協議により、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所の審判により定められるものであり、遺留分減殺請求訴訟において、抗弁として主張することは許されないと解するのが相当である。」
4 財産評価の基準時について
遺留分の算定を行うにあたって基礎となる財産の評価時点は、相続開始時点であるとされています。これは、遺留分という権利が相続開始と同時に具体的に発生するためであり、その時点における財産の状況をもって算定の基礎とする必要があるからです。
生前に贈与された財産についても同様の考え方が適用されます。すなわち、贈与が行われた当時の価額ではなく、相続が開始された時点においてその贈与財産の価額を再評価し、その額をもって遺留分算定の基礎とすることになります。
さらに、相続が開始した後に財産の評価額に変動が生じた場合であっても、あくまで相続開始時点における評価額が基準となりますので、遺留分侵害額を算定する上では考慮されません。
5 遺留分侵害額の計算
⑴ 遺留分侵害額の具体的な計算は次のような手順で行われます。
① 遺留分額の算定
最初に、遺留分権利者に保障されている「遺留分額」を算出します。
遺留分額は、遺留分を算定するための財産の価額(3⑴参照)に、個別的遺留分(2⑵参照)を乗じることで算出されます(民法第1046条第2項柱書、民法第1042条)。
② 遺贈・特別受益の控除
次に、遺留分権利者が被相続人から受けた遺贈や特別受益がある場合には、その価額を①で算出した遺留分額から控除します(民法第1046条第2項第1号)。
なお、遺留分権利者の遺留分額から控除される特別受益については、遺留分算定の基礎となる財産に算入される特別受益(3⑵イ参照)と異なり、相続開始前の10年間に限定されることはありません。
③ 遺産分割によって取得した財産の控除
さらに、遺言によって分割方法等が指定されていない遺産がある場合に、遺留分権利者が遺産分割手続により取得した財産については、その評価額も遺留分額から控除されます(民法第1046条第2項第2号)。
④ 相続により負担した債務の加算
一方で、遺留分権利者が相続に伴って現実に負担することとなった債務がある場合には、その債務額を加算することが認められます。
ここで加算されるのは、法定相続分に応じた抽象的な額ではなく、実際に遺留分権利者が負担することになった債務の額です(第2項第3号)。
⑵ 上記の計算の結果遺留分侵害がある場合、遺留分権利者は、侵害額に相当する金銭の支払いを遺留分侵害額請求として求めることができます。
3 遺留分侵害額請求権の行使
1 請求の相手方
⑴ 遺留分侵害額請求の相手方
① まず、遺言によって財産を受け取った相続人又は受遺者に請求します(民法第1047条第1項第1号)。
② ①の請求をしても遺留分侵害額に不足があるときは、生前贈与を受けた受贈者に請求します(民法第1047条第1項第1号)。
③ 生前に複数回の贈与がなされている場合、遺留分の満足を受けるまで、新しい贈与から古い贈与に遡って請求します(民法第1047条第1項第3号)。
⑵ 死因贈与の扱いについて
死因贈与がなされていた場合の扱いについては、「遺贈と同様に扱う」とする説と、「遺贈と生前贈与の中間的性質を有する」とする説があり、判例および学説は未だ定まっていません。民法の相続に関する規定が改正された際(令和元年7月1日施行)においても、死因贈与に関する明文規定の整備は見送られました。
この点について判断した下級審の裁判例としては、東京高判平成12年3月8日高民53巻1号93頁があり、「遺贈に次いで、生前贈与より先に減殺の対象とすべき」と判示しています。
2 相手方の負担額
遺留分侵害額請求を受けた相手方の負担額は、遺言または生前贈与により受け取った財産の価額を上限とします。ただし、請求を受けた者が相続人である場合には、その者自身の遺留分相当額を控除した額が上限となります(民法1047条1項柱書)。
なお、遺留分侵害額請求の相手方が複数いる場合には、それぞれが遺言または贈与により受けた財産の「目的の価額」の割合に応じて負担することになります(同条1項2号本文)。
3 請求の手段
⑴ 意思表示
遺留分侵害額請求権は、意思表示によって行使する必要があります。
したがって、遺留分侵害額を請求するという意思表示をしない限り、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利(金銭債権)は発生しません。
また、遺留分侵害額請求の意思表示は、必ず書面により行わなければならないわけではありません。しかし、遺留分侵害額請求には時効(1年)や除斥期間(10年)といった期間制限があるため(詳細は後述)、内容証明郵便等により、遺留分侵害額請求の意思表示が相手方に到達した日が明確に分かるようにしておくことが望ましいといえます。
なお、遺留分侵害額請求権の行使は、あくまで遺留分を請求するという意思表示を行うことで足りますので、意思表示の時点で遺留分侵害額(請求額)を具体的に明らかにする必要はありません。
⑵ 調停
遺留分侵害額請求の意思表示を行い、相手方と交渉をしても話がまとまらない場合は、調停を申し立て、裁判所(調停委員)を交えた話し合いに移行します。
遺留分侵害額請求においては、訴訟提起よりも先に調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法第257条第1項、調停前置主義)。
もっとも、紛争の経緯等その実態に照らして調停による解決が期待できないような場合は、調停を経ずに訴訟提起をすることが可能です(家事事件手続法第257条第2項但し書き)。
⑶ 訴訟
調停でも話し合いがまとまらない場合や、そもそも調停では解決が期待できない場合は、訴訟を提起し、訴訟手続の中で遺留分侵害額やその根拠等を明らかにしていくことになります。
4 時効及び除斥期間
⑴ 遺留分侵害額請求の期間制限について
遺留分侵害額請求には時効が定められており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内に請求しない場合は、時効により請求ができなくなります(民法第1048条前段)。
また、除斥期間の定めもあり、相続の開始から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求を行うことはできなくなります(民法第1048条後段)。
なお、時効及び除斥期間の範囲内で遺留分侵害額請求権が行使された場合、それによって生じる金銭債権は通常の金銭債権と同様に扱われ、5年で時効により消滅することになります(民法第166条第1項第1号)。
⑵ 「知った時」の意義:遺言無効の主張との関係
遺留分侵害額請求は、遺言が有効であることを前提とする請求です。したがって、たとえ遺言や生前贈与の内容を遺留分権利者が知っていたとしても、その遺言や贈与が無効であると信じていた場合に、「遺留分が侵害されていることを「知った時」といえるかが問題となります。これは、時効の起算点との関係で重要な論点です。
この点について、最判昭和57年11月12日民集36巻11号2193頁では、「無効の主張について、一応、事実上及び法律上の根拠があって、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことがもっともと首肯しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知っていたものと推認するのが相当というべきである。」と述べた上で、生前贈与が公序良俗違反により無効であると主張していた遺留分権利者の主張について、法律的根拠を欠くため「特段の事情」が認められないとして、遺留分減殺請求を否定しました。
このように、「特段の事情」という例外的な事情が認められない限り、遺留分侵害額請求の時効は進行するものと解されます。したがって、仮に遺言の無効を主張する場合であっても、念のため、遺留分侵害額請求も併せて行っておくことが重要です。
⑶ 除斥期間の例外
除斥期間にも、例外が認められる場合があります。
仙台高判平成27年9月16日判時2278号67頁は、以下のような事情のもとで、除斥期間の適用が否定されました。
この事案では、相続人Aが、遺言書について、司法書士から、「開封されているため、遺言としての効力はない」旨聞かされたと述べたことから、遺言は無効であることを前提として遺産分割協議が継続されていました。ところが、相続の発生から10年以上経過した段階で、相続人Aは、「遺言書を司法書士に見せたところ、有効な遺言であるとの説明を受けた」と述べました。
このような事案において、裁判所は、「相続開始の時から10年間にわたり、有効な遺言が存在することを認識し得ず、その結果、遺留分減殺請求権を行使することを期待できない特段の事情があったと認めるのが相当である。・・・遺留分権利者・・・が、上記特段の事情が解消された時点から六か月以内に同権利を行使したと認められる場合には、控訴人について、・・・遺留分減殺請求権消滅の効果は生じないものと解するのが相当である。」と判示しました。
4 遺留分侵害への事前対策
遺留分侵害による紛争を防ぐためには、事前に適切な対策を講じることが重要です。遺留分侵害を防ぐための主な対策としては、遺言を作成する際に遺留分に配慮した内容を盛り込むことや、事前の遺留分放棄を行うことが挙げられます。
1 遺留分に配慮した遺言の作成
遺留分権利者の遺留分を考慮せずに遺言を作成すると、遺留分侵害が発生し、遺留分権利者が遺留分侵害額を請求する事態が発生する可能性があります。
そのため、遺言作成にあたって、遺留分侵害額請求をなるべく避けることを重視する場合には、遺留分権利者が受け取るべき最低限度の財産を確保しながら残りの財産を配分することで、円滑な財産承継が可能となります。
もっとも、遺言を作成した時点で遺留分を守るよう配慮しても、その後の財産価値の変動や新たな財産の取得により、遺留分権利者の遺留分が侵害される可能性があることには注意が必要です。
2 遺留分放棄
⑴ 遺留分権利者は、相続が発生する前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することが可能です。この遺留分放棄が事前に行われている場合には、遺留分を侵害する内容の遺言に対して、遺留分権利者が後から異議を唱えることを防ぐことができます(民法第1049条第1項)。
遺留分放棄を行うことは、遺留分権利者が相続に関して有する最低限の権利を放棄することと同義です。したがって、家庭裁判所は、権利者の自由意思によるものか、放棄理由の合理性・必要性、放棄と引き換えの代償の有無などを考慮して、相当と認めるときに限り遺留分放棄を許可することになります。
なお、被相続人の生前に遺留分を請求しない旨の合意をしていた場合、事情によっては、遺留分放棄につき家庭裁判所の許可を得ていない場合でも、遺留分侵害額請求が認められない可能性があります。
たとえば、東京地判平成11年8月27日判タ1030号242頁は、次のような事案について判断を示しています。
この裁判例では、原告らの父が、過去の裁判上の和解において、その母(原告らの祖母)の将来の相続分に相当する財産をすでに取得したことを認め、将来において母の相続分および遺留分を請求しないことを約束していました。しかし、遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を得る手続は取られていませんでした。原告ら祖母の相続が発生した後、代襲相続人である原告らは、遺留分減殺請求(※当時の制度)を行いました。しかし、裁判所は、「家庭裁判所の許可の手続が履践されていないことを奇貨として、遺留分減殺請求権を行使することを認めるならば、本件和解の合意に反し、原告らに二重取りを許すことになり、著しく信義に反することになる」と述べて、遺留分減殺請求権の行使を認めませんでした。
このように、形式的には遺留分放棄の要件を満たしていなくても、信義則に基づき遺留分侵害額請求が制限されることがあります。
⑵ なお、相続発生後であれば、遺留分権利者は家庭裁判所の許可を得ることなく、遺留分を放棄することができます。遺留分放棄の意思表示は、遺留分侵害額請求の相手方に対して行う必要があります。