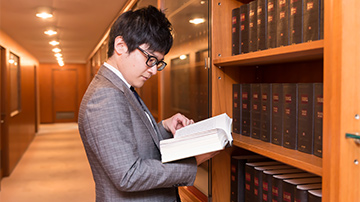最重要実務解説
遺産分割
2025.07.24
1 遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人の財産を相続人間で分ける手続きをいいます。相続人が複数いる場合、誰がどの財産を取得するかを相続人全員で協議し、決定する必要があります。
以下では、遺産分割の重要なポイントについて詳しく解説します。
関連記事:遺産分割について
2 遺産分割手続の種類
⑴ 遺言による分割
遺言によって遺産の分割方法が指定されている場合には、原則として遺言のとおりに遺産を分割します。
⑵ 遺産分割協議による分割
遺言が存在しない場合や、遺言があっても無効であったり遺産の分割方法に関する指定が不明確であったりする場合には、相続人全員で協議を行い、遺産の分割方法を決定します。
⑶ 家庭裁判所による分割(調停・審判)
相続人間で協議がまとまらない場合や協議に応じない相続人がいる場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員を交えて遺産の分割方法を話し合うことができます。
調停でも話し合いがまとまらなければ、調停は不成立となり、遺産分割審判に移行して、裁判官が遺産の分割方法を決定します。
3 遺産分割方法の種類
遺産の分け方には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4つの方法があります。いずれの方法によるかは、当事者の意思を尊重して決めることになりますが、当事者の合意が整わないときは、家庭裁判所が決定することになります。
上記4つの分割方法のうち、基本的には、現物分割が原則的な分割方法であり(最判昭和30年5月31日)、「特別の事情」がある場合には、代償分割ができるとされています(家事事件手続法195条)。
現物分割や代償分割がいずれも相当でないときにはじめて換価分割ができ、換価分割もできない事情がある場合にはじめて共有分割ができるとされています。
⑴ 現物分割
現物分割とは、相続財産を、現物そのままの形で分割する方法をいいます。遺産分割の多くは、この現物分割の方法により行われています。
(例)Aアパートは長男、Bアパートは次男が取得する。
⑵ 代償分割
一部の相続人が特定の遺産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法です。
(例)長男が自宅土地建物を取得する代わりに、次男に現金を支払う。
不動産や事業用資産など、物理的に分けることができない遺産を売却せずに利用したい相続人がいる場合には、代償分割が有効な方法となります。
代償分割が認められるためには、①遺産の評価が適正で、代償金の額が適正であることを前提に、②具体的相続分を超える遺産を貰う相続人に、代償金の支払い能力があることが必要です(最判平成12年9月7日日)。通常は、金融機関の預金通帳の写しや、残高証明書の写しを、家庭裁判所に提出して、不動産を相続する相続人が十分な支払能力を有していることを証明することになります。
⑶ 換価分割
遺産を売却して現金化し、その代金を相続人間で分ける方法です。
(例)C土地を第三者に売却し、売却代金を相続人間で均等に分ける。
不動産などの物理的に分けることができない遺産については、遺産を売却することによって、その代金を相続人間で公平に分けることが可能です。
相続人に代償金を支払えるだけの資力がないため、代償分割ができない場合や、誰も現物の取得を希望しない場合等に用いられます。
裁判手続における換価方法として、調停における任意売却、終局審判における競売による換価、中間処分としての競売又は任意売却による換価(家事事件手続法194条1項2項)があります。
⑷ 共有分割
共有分割とは、不動産等を相続人の共有にする分割方法をいいます。共有分割が行われた場合、その後の共有状態を解消するには、相続人間で共有物分割という手続が必要です。
遺産が共有状態のままだと、遺産を処分するには、共有者となっている相続人全員の同意が必要になります。そのため、たとえば相続人の中に不動産の売却に反対の人がいた場合には、その人からの同意が得られず、不動産を売却できない事態が生じます。
このように、遺産の共有は相続人間の紛争を根本的に解決したことにならないことが多いため、共有分割が認められるのは、他の分割方法によるのが相当でない、例外的な場合に限られます。具体的には、現物分割や、代償分割によることが相当でなく、しかも換価をすることが相当でない場合や、相続人の全員が遺産を売却して代金をそれぞれの相続人に分配することを合意している等、共有分割の方法を用いることが特段不相当とはいえない場合に限られます。
関連記事:分割方法の決定と遺産分割協議のポイント
4 遺産分割の手続きの流れ
遺産分割は、被相続人の相続が開始した後、遺言の有無を確認するところから始まります。ここでは、一般的な流れを解説します。
⑴ 遺言の有無の確認
遺言の有無によって遺産分割協議の要否やその対象となる遺産の内容が変わってくるため、まずは遺言の有無を確認します。
遺言がある場合には、原則として遺言に基づき遺産分割を行います。
⑵ 相続人の確定
遺産分割は相続人全員で行う必要があるため、戸籍を調査するなどして相続人の範囲を確定します。
⑶ 遺産の調査・評価
遺産分割の対象となる遺産の種類(不動産、預貯金、株式、負債など)を調査し、その価値を評価します。
⑷ 遺産分割協議
遺言がない場合や、遺言があっても無効であったり遺産の分割方法に関する指定が不明確であったりする場合には、相続人全員で協議を行い、遺産の分割方法を決定します。
協議が成立したら、その内容を遺産分割協議書にまとめて、相続人全員が署名押印します。
⑸ 調停分割(遺産分割調停)
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、そもそも協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停を申立てることができます。
調停を行って相続人間で合意が成立すれば、調停が成立したこととなり、遺産分割調停の手続は終了します。
調停が成立すると、確定した審判と同一の効力を有することになり、調停調書をもって相続手続(不動産の相続登記、預貯金の解約等)をすることができます。
⑹ 審判分割(遺産分割審判)
遺産分割調停が不成立になった場合には、遺産分割の審判となり裁判官(家事審判官)が遺産の分割方法を決定し、強制的に遺産を分割することになります。審判分割では、法定相続分を基準とした分割が行われます。
なお、調停が不成立で終了した場合には、当然に審判手続に移行することとされていますので、別途家庭裁判所に審判の申立てをする必要はありません。
弁護士に依頼すれば、これらすべての行程でサポートが受けられ安心です。
遺産分割には法的判断・書類作成・交渉・裁判所対応など、多くの専門知識が必要です。弁護士に相談・依頼することで、相続人間の調整、協議書の作成、調停・審判対応など、すべてのステップで専門的な支援を受けられます。
特に相続関係が複雑な場合や感情的な対立がある場合には、弁護士の介入が円滑な解決に大きく寄与します。
5 遺産分割手続における共通の問題点
⑴ 相続人の範囲の問題
ア 相続人の範囲の確定の必要性
誰が相続人になるのかが分からなければ、そもそも協議ができません。また、遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を欠いた遺産分割協議は、無効です。
そのため、まずは相続人の範囲を確定する必要があり、相続人の範囲を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。
法定相続人の範囲は、常に相続人となるのが配偶者、第1順位として直系卑属(子や孫)、第2順位として直系尊属(両親や祖父母)、第3順位として兄弟姉妹(又は死亡している兄弟姉妹の子(甥姪))となります。配偶者は他の相続人がいても常に相続人となり、その他の法定相続人は上位の順位者が存在しない場合にのみ相続人となります。
相続人の範囲が確定すれば、法定相続分が決定します。相続人が配偶者と第1順位の相続人の場合はそれぞれ2分の1ずつ、配偶者と第2順位の相続人の場合は配偶者が3分の2、第2順位の相続人が3分の1、配偶者と第三順位の相続人の場合は配偶者が4分の3、第三順位の相続人が4分の1となります(同順位の法定相続人が複数存在する場合は人数で均等割します。)。
なお、相続人を確定したとしても、数次相続(相続人が死亡した場合)、相続放棄・相続分譲渡、死後認知の訴え、相続欠格・相続廃除などの事情が発生すれば、相続人の範囲や相続分が変更しますので注意が必要です。
また、遺産分割手続を行う相続人には、意思能力(自分の行為の結果を弁識し、判断できる能力)や行為能力(確定的に有効な法律行為を行う能力)が必要です。もし、遺産分割協議が形式上行われたとしても、相続人の中に意思能力や行為能力のない人がいた場合には、遺産分割協議は無効であったり後で取り消されたりすることになりますので、そのような相続人がいる場合には別個の手当てが必要になります。
イ 意思能力がない相続人がいる場合
認知症などにより意思能力がない相続人がいる場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、成年後見人を協議に参加させて、遺産分割協議を進めていく必要があります。
ウ 相続人に未成年者がいる場合
相続人に未成年者がいる場合には、その未成年者の親権者(父母)が、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加するか、または成年に達するまで待つことが必要です。なお、親権は共同行使が原則とされていますから、未成年者の父母が共同して(ただし、一方が親権を行うことができないときは、他の一方のみで)遺産分割協議に参加することになります。
親権者である父母もまた相続人となる場合や未成年者が複数いる場合、そのまま父母が代理人となると利益相反となってしまうので、そのような場合は、家庭裁判所に申し立てて、特別代理人を選任する必要があります。
エ 行方不明の相続人がいる場合
相続人の所在については、戸籍の附票や住民票を取り寄せて住所を調べますが、それでも所在不明の相続人がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、その不在者財産管理人を遺産分割協議に参加させることになります。
行方不明者の生死が7年間明らかでない場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。これにより、行方不明者の生死がわからなくなった時から7年後に死亡したものとみなしてもらうことができます。
失踪宣告により、その行方不明者は法律上死亡したものとみなされますので、その行方不明者を除いて遺産分割協議を成立させることができます。
⑵ 遺産分割の対象となる遺産の範囲の問題
被相続人が相続開始時に有していた権利・義務は、原則としてすべて相続の対象となり、相続人に承継されます。
しかし、相続の対象となるかということと、相続の対象となるとしても遺産分割(遺産分割審判)の対象となるかということとは法的に区別して考えられています。
遺産分割の対象から除かれて扱われる遺産がありますので、財産の種類ごとにご説明します。
ア 現金
被相続人の財布の中に入っていた現金や、金庫等に置かれていた現金ですが、相続の対象になることはもちろんですが、遺産分割の対象になるかどうかは議論があり得るところです。
この点、最高裁の判例によって、遺産分割の対象となることが示されました(最判平成4年4月10日)。
イ 金銭債権
他者への貸付金などの金銭債権については、実務上、相続開始とともに法律上当然分割されると解されており、遺産分割の対象にならないとされています。
ただ、相続人間の合意があれば、金銭債権であっても遺産分割の対象とすることができると解されています。
ウ 預貯金
預貯金は、法律上は預貯金債権といわれ、金銭債権のひとつとして扱われます。
預貯金が遺産分割の対象になるかどうかは議論があり、多くの裁判例でも争われてきました。この議論については、平成28年の最高裁決定で、預貯金は遺産分割の対象財産であるという結論が示されました(最大決平成28年12月19日)。
そのため、今後は預貯金も原則として遺産分割の対象財産に含まれることとなります。
エ 不動産
土地や建物といった不動産が遺産分割の対象になることに争いはありません。被相続人名義の不動産について、誰がどのように取得するかを決定することになります。
オ 不動産賃借権(借地権、地上権、借家権等)
たとえば、被相続人が借家に住んでいた場合等には不動産賃借権が相続の対象となり、遺産分割の対象となります。
カ 株式
一般的に、株式会社の株式については、相続人全員の(準)共有状態になり、遺産分割の対象になります(所有権以外の財産権を複数名で有する場合、共有に準じて「準共有」と呼ばれます。)。
遺産分割協議が成立した後は、株式を承継することとなった相続人が名義書換を行って、単独で議決権を行使することになります。
他方で、遺産分割前の準共有状態の株式の議決権は、どのように行使するかという問題が生じます。会社法では、株式が2人以上の者の共有に属するときは、共有者は、その株式について権利を行使する者1人を定め、株式会社に対してその者の氏名又は名称を通知しなければ、その株式について権利を行使することができない、と規定されています。
そのため、相続人間の協議で、株式の権利行使者1名を選んで、それを会社に通知し、その権利行使者が議決権を行使することになります。
相続人間で権利行使者の希望が合致しない場合には、持分の過半数を有する相続人(相続人グループ)が希望する者を、権利行使者として選定することになります。
キ 投資信託
投資信託と呼ばれる金融商品については、その種類によって若干取扱いに差がありますが、通常、信託受益権等が遺産分割の対象になるものと扱われています。
ク 国債
個人の投資家が購入する個人向け国債は、遺産分割の対象になるものと扱われています。
ケ ゴルフ会員権
ゴルフ会員権には、預託会員制、株主会員制、社団会員制の3つの形態があり、このうち預託会員制がほとんどだといわれています。また、裁判例の中には、「ゴルフクラブの会員たる資格」や「会員権者たる資格」といった区別がされているものがあります。
一般的には、預託会員制のうちゴルフクラブの会則が相続性を肯定している場合には、遺産分割の対象となります。
実際には、ゴルフクラブを経営する会社や理事会の承認等が必要になることが多いので、個別に問合せをして確認することが必要です。
コ 生命保険金
生命保険金は、保険金受取人が被相続人によって指定されていたり、保険約款によって保険金受取人が定められており、その受取人の固有の権利として保険金請求権を取得することになりますので、遺産分割の対象とはなりません。
ただし、生命保険金の金額が著しく高額で、他の相続人との間の公平性が大きく損なわれる場合には、特別受益として遺産分割の中で考慮されることがあります。
サ 遺産から生じた果実(収益)
相続開始後に遺産から生じた収益(たとえば、賃貸不動産の賃料収入や、利息、配当金等)は、相続財産ではないため、当然には遺産分割の対象になる財産として扱われません。
ただし、実務上は、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象として扱うことが認められています。
〇 最高裁平成17年9月8日判決
最高裁は、賃料収入が遺産分割の対象になるか等が問題となった事案について以下のように判断しています。
相続発生から遺産分割までの間に、遺産である不動産を賃貸して得られる賃料は、遺産とは別個の財産である。
不動産を賃貸して得られる賃料(賃料債権)については、各相続人はその相続分に応じ、分割単独債権として確定的に取得する。
各相続人が確定的に取得した賃料(賃料債権)は、後になされる遺産分割によって賃貸不動産の承継者が決定した場合でも、影響を受けない。
シ 相続債務
相続開始前の金銭債務は、相続によって各相続人に法定相続分に応じて当然に分割されて承継されると考えられており、遺産分割の対象とはなりません。
もっとも、相続人全員の同意があれば、遺産分割の対象になる財産として扱うこともできます。ただ、債務の承継については、通常、債権者の承諾が必要になるので、相続人間で債務の負担割合を協議したとしても、その結果を債権者が承認しない限り、債権者との関係では法定相続分に応じた債務を負うことになります。
ス 葬儀費用、香典
葬儀費用は、たとえばお通夜の費用や、葬儀告別式の費用、納骨代等をいいます。初七日や四十九日の費用については、見解が分かれるところです。
また、香典は、法的性質としては遺族が支払う葬儀費用を一部負担する趣旨で贈与されるものと扱われています。
葬儀費用や香典は、被相続人の遺産ではなく、誰がどのように負担・清算するかは確定的には決まっていません。喪主の負担とされることが比較的多いですが、相続人全員の合意をもって遺産分割において清算することもあり得ます。
セ 使途不明金
一部の相続人が、被相続人が死亡する前や死亡した後に、被相続人の預貯金を引き出して使い込んだことが疑われる場合があります。
被相続人のための医療費や介護費用に使われたものであれば特に問題はありませんが、被相続人のために使われたものでなく、そもそも何に使われたのか分からないという場合が問題になります。
使途不明金について相続人間の協議で解決できれば大きな問題にはなりませんが、遺産分割調停や審判を行うようなケースでは使途不明金について大きな争いになることが多いです。
このような争いについては、遺産分割調停・審判とは別に、使い込みが疑われる相続人に対して、民事訴訟(不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得の返還請求)を提起して、解決することになります。
とはいえ、民事訴訟を提起したとしても、使い込みの事実を立証することには相当のハードルがあります。使途不明金の引き出しの時期や、被相続人の当時の状態、被相続人と相続人の関係(日常生活の世話をしていたのか、同居していたのか等)を詳しく精査して、訴訟の見通しを検討する必要があります。
⑶ 遺産の評価の問題
遺産分割の対象となる財産が確定したら、次にそれらの財産の価値を評価する必要があります。
遺産の客観的な価値は、絶えず変動しています。そのため、いつの時点を基準に遺産の価値を評価するのか、という問題があります。
基準時が問題になるのは、各相続人の法定相続分を、特別受益や寄与分によって修正して具体的相続分を算定する段階と、その具体的相続分に従って遺産を現実に分配する段階の2つの段階があります。
特別受益や寄与分によって各相続人の法定相続分を修正して具体的な取得割合を算定する段階では、相続開始時を基準とするのが実務の取扱いです。他方で、現実に遺産を分配する段階では、遺産分割時を基準とするのが実務の取扱いです。
預貯金や金融資産については、金額が明確なので争いになることは多くありません。遺産の評価で争いになりやすいのは、不動産や非上場株式です。
ア 不動産の評価
遺産の評価にあたって、相続人間で争われることが最も多いのが不動産です。不動産の評価方法は多種多様であり、またそれぞれの評価方法によって評価額に大きな差が生じることも多々あります。
遺産分割協議では、不動産をどのような方法で評価するのか、相続人間で合意形成を試みます。合意形成を試みる際には、以下のような公的な評価基準が参考になります。
① 固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に記載された固定資産税の課税の基準となる土地・建物の評価額のことをいい、一般的に公示地価の約7割程度の金額となることが多いです。固定資産税評価額は、固定資産税の課税明細書や、評価証明書によって記載されており容易に確認することができるため、固定資産税評価額で合意が得られることもありますが、実際の取引価格よりも低い場合が多いので、合意が得られないことも多いです。
② 相続税評価額(路線価、倍率評価)
路線価は、毎年7月1日に国税庁が公表している、一定の道路に接する土地の評価額です。1月1日時点の地価公示価格、不動産鑑定士などの専門家による評価、精通者の意見などを反映させ、国税局が評価額の基準を定めたうえで決定し、国税庁公式ウェブサイトの「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」上で公開しています。
路線価は一般的に公示地価や時価の約8割程度であり、主に相続税や贈与税申告時に用いる評価額です。
容易に確認することができるため、路線価で合意が得られることもありますが、実際の取引価格よりも低い場合が多いので、合意が得られないことも多いです。
③ 公示地価
公示地価は、国土交通省土地鑑定委員会が地価公示法に基づき、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を毎年3月に公示するものです。
公示地価は、主に不動産取引で用いられる価格、不動産鑑定の基準価格の指標になる時価に近い金額となることが多いですが、全ての土地の評価がなされるわけではなく、標準地のみ評価がなされます。
④ 都道府県地価調査価格(基準地標準価格ともいいます。)
国土利用計画法施令第9条に基づき、都道府県知事が、毎年7月1日時点における標準価格を判定するものです。
これらの公的基準を参考にしても合意が得られない場合には、時価(実際に取引される価格)を算定する必要があります。時価を算定する場合には、不動産鑑定士が行う鑑定評価額が最も信頼できる評価方法であるとされています。
鑑定には、各相続人がそれぞれ不動産鑑定士に依頼して行う私的鑑定と、遺産分割調停・審判手続において家庭裁判所が不動産鑑定士を選定して行う公的鑑定があります。
イ 非上場株式の評価
非上場株式は、市場で取引されるものではないため、上場株のような市場価格というものが存在しません。
したがって、非上場株式が遺産に含まれている場合には、その価値を算定する必要があります。
非上場株式の評価方法としては多様なものがありますが、一般的には下記の通りインカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、ネットアセット・アプローチの3体系に分類されます。そして、その各体系の中でも更に複数の評価方法が存在しています。
① インカム・アプローチ
インカム・アプローチは、評価対象会社が将来獲得しうる収益やキャッシュ・フロー(現金収支)に対し、獲得が実現できるリスクなどを反映し企業価値を評価する方法です。
代表的な評価方法としては、①DCF法(企業が将来獲得するであろうキャッシュ・フローを資本還元率で現在価値に還元する方式)、②収益還元法(評価対象会社が長期的に獲得できると見込まれる会計上の純利益の平均値を、一定の割引率で割り引くことによって評価する方法です。)、③配当還元法(株主が将来獲得できると見込まれる配当金額を、通常の配当性向が維持されるとの前提をもとに、株主資本コストで割り引いて評価する方法)があります。
② マーケット・アプローチ
マーケット・アプローチは、上場している同業他社の株価や類似する取引事例などと比較することによって相対的に価値を評価する方法です。
代表的な評価方法としては、①類似企業比較法(評価対象会社と、それと類似する上場会社の一株あたりの利益や純資産などの財務数値を比較して算出した倍率を、上場会社の市場株価にかけて評価会社の株価を算出する方法)、②取引事例法(評価会社の株式について過去に行われた取引の価格を参照して評価する方法)があります。
③ ネットアセット・アプローチ
ネットアセット・アプローチは、貸借対照表の純資産を基準に株価を算定する方法です。
代表的な評価方法としては、①時価純資産法(貸借対照表の資産及び負債を評価時点の時価で再評価し、時価ベースの純資産額をもって株式の価値とする評価方法)、②簿価純資産法(貸借対照表の純資産の帳簿価額をそのまま株式の価値とする評価方法)があります。
上述の通り、非上場株式の評価方法としては様々な種類があり、各評価方法によって金額が異なることも多くあります。
適正な評価をするためには、どの評価方法を用いるか或いはどの評価方法とどの評価方法をどのような割合で組み合わせるかを、評価対象株式ごとに適正に判断する必要があります。
その最終的な総合評価の方法としては、下記の三通りの方式があります。
① 単独法
インカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、ネットアセット・アプローチの各評価アプローチに属する評価方法の中から1つの評価方法を適用し、評価を行う方法です。
② 併用法
各評価アプローチに属する評価方法の中から複数の評価方法を適用し、それぞれの評価結果が重複するレンジをもって評価結果を導く方法です。一定の幅をもった評価額とする場合と、レンジの中央値を評価額として示す方法があります。
③ 折衷法
各評価アプローチに属する評価方法の中から複数の評価方法を適用し、各評価方法の結果に一定の折衷割合を適用して、それらの加重平均値として評価額を算出する方法です。
実際に非上場株式の評価を行う際、これらの評価手法のうちどれをどのように適用すべきかについては、一律に決定されるものではなく、評価対象株式の具体的状況に応じて判断されることとなります。例えば、評価対象会社の事業内容、収支状況、資産構成や資本政策等によって異なりますし、対象株式の量(経営権に対する影響度合い)、株主構成等によっても異なります。
非上場株式の評価について当事者間の合意が得られない場合は、不動産の場合と同様、非上場株式の鑑定評価を行うことになります。非上場株式の鑑定は、公認会計士等の専門家が行うことになります。
⑷ 特別受益・寄与分の考慮の問題
ア 具体的相続分の算定
遺言書がない場合には、民法が規定する法定相続分に沿った遺産分割が行われることになりますが、法定相続分どおりの遺産分割が、決して公平とはいえない場合が生じます。
例えば、相続人の一人が被相続人と生活を共にしていて、24時間介護が必要な被相続人の世話を長年にわたって行うなどしていたような場合、介護をしていた相続人と、その他の相続人が同じ相続分であるのは不公平となる場合があります(寄与分の問題)。
また、相続人の一人が、私立の医学部を卒業させてもらった、住宅購入のための資金を贈与してもらったなどの場合に、その方が他の相続人と同じであるのも同様に不公平です(特別受益の問題)。
このような不公平を是正するために、民法は、特別受益と寄与分という調整のための制度を設けており、この調整を行った後の相続分のことを具体的相続分といいます。
イ 特別受益について
(ア)特別受益とは
相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ法定相続分で遺産を相続してしまうと、不公平になる場合があります。
そこで、民法は、相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を計算することにしています。これを特別受益といいます。
(イ)特別受益がある場合の計算方法
特別受益がある場合は、相続発生時の遺産に、特別受益となる財産を加算して、実質的な遺産の額を算出します。この実質的な遺産額をみなし相続財産といいます。
次に、みなし相続財産に各人の法定相続分を乗じて、各人の取得分を算出します。特別受益がある相続人については、その取得分から特別受益分を控除した分が、相続の際に取得する具体的相続分となります。
<計算例>
相続開始時の遺産4000万円、子ABのうちBのみ被相続人の生前に2000万円の生前贈与(特別受益)があったという場合
・みなし相続財産:4000万円+2000万円=6000万円
・各人の取得分:6000万円×1/2=3000万円
・Aの取得分(具体的相続分):3000万円
・Bの取得分(具体的相続分):3000万円-2000万円=1000万円
(ウ)特別受益の種類
特別受益には、遺贈、婚姻又は養子縁組のための贈与、その他の生計の資本としての贈与の3類型があります。
生前贈与の全てが特別受益となるわけではありません。生前の贈与が特別受益に該当するかどうかは、その贈与が「相続財産の前渡し」にあたる贈与かどうかを基準として判断することになります。
【婚姻又は養子縁組のための贈与について】
① 持参金、支度金
結婚の際の持参金、支度金として贈与を受けた場合は、一般的に特別受益に該当するとされています。但し、贈与された金額が少額である等、被相続人の資産や生活状況を考慮して、扶養の一部として贈与したものと認められる場合には、例外的に特別受益にあたらないと解されることもあります。
② 結納金、挙式費用
原則として特別受益に該当しません。
【その他の生計の資本としての贈与について】
① 学費
たとえば複数名の子の内、1人だけが私立の医学部に通い多額の学費がかかった場合等は、特別受益に該当すると考えられます。他方で、子全員に同程度の学費がかかった場合等は、特別受益として考慮されません。
② 生活費等の贈与
働いていて十分収入がある子に対し、親が定期的に生活費の名目で金銭を贈与していた場合は、特別受益に該当することがあります。他方で、精神的・身体的理由により働けない子どもに対して、親が生活費を援助する場合は、親の扶養として特別受益にはあたらないと考えられます。
③ 営業資金の贈与・債務の肩代わり
自営業を営む子どもに対し、親が営業資金や独立開業資金を贈与した場合は、特別受益に該当すると考えられます。また、子どもの借金を親が代わりに支払い、その後子どもに求償していない場合も特別受益に該当すると考えられます。
④ 生命保険金
受取人となっている特定の相続人が死亡保険金を取得した場合は、原則として特別受益にはなりません。但し、その保険金の金額が、相続財産の大部分を占める場合には、例外的に特別受益に準じるものとして、後述の持戻しの対象となる場合があります。
⑤ 遺産を無償で使用できることによる利益
遺産である土地の上に相続人の1人が建物を建て、土地を無償で使用している場合と、遺産である建物に相続人の1人が居住している場合があります。
この相続人は、遺産である土地や建物を無償で占有することができることになり、他方、被相続人の遺産の価値は、その占有により使用借権相当額(土地であれば更地価格の1割から3割)の減少があると見ることができます。
(エ)特別受益の持戻しの免除
特別受益の持戻しは相続人間の公平を図ると同時に、 被相続人の合理的意思を推測した算定方法ですから、 被相続人が持戻しをしない旨の意思表示をした場合には、持戻しを行わないことになります。これを特別受益の持戻しの免除といいます。
持戻免除の意思表示は、特別の方式を必要としません。また、生前行為によっても、遺言行為によっても行うことが可能です。
なお、2019年7月1日以降に、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して居住用建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について特別受益の持戻しの規定を適用しない旨の意思表示をしたものと推定されます(民法903条4項)。
持戻しの免除が行われれば、各人の具体的相続分の算定にあたって特別受益は考慮されません。その場合、遺言による分割方法の指定がない遺産(相続人間の共有となる財産)に各人の法定または指定の相続分を乗じたものが、各人の具体的相続分となります。
持戻しの免除の意思表示は、明示の意思表示である場合はほとんどなく、黙示の意思表示が認められるかどうかが実務上問題となります。
例えば、①身体的、精神的障害があるために経済的に恵まれない相続人に対し、将来の扶養の意味も含め贈与等がなされた場合、②子がない、又は子からの扶養を期待できない妻に対して生命保険金を取得させた場合、③被相続人と同居して世話をしてもらうために土地や建物の使用権を与えた場合、④寄与相続人に対しその寄与に報いるために贈与等がなされた場合、⑤金銭には評価されにくい貢献に対してその貢献に報いるために贈与等がなされた場合などが、持戻し免除の黙示の意思表示を推定させる事情として考えられます。
(オ)特別受益の立証
他の相続人に特別受益があったことを主張する相続人は、特別受益があった事実を立証する責任を負い、立証できなければ特別受益は認められません。受益の時期、金額、内容を具体的に明らかにして、それを裏付ける証拠を提出しなければなりません。
特別受益の立証や証拠の収集方法については、相当に専門的な知識・経験を必要とすることが多いといえます。また、証拠の収集のために、弁護士の職権による調査を行う必要が生じる場合も多々あります。
ウ 寄与分について
(ア)寄与分とは
相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした者がいる場合に、その者の相続分に特別の加算を行うのが寄与分の制度です。
例えば、被相続人の家業を長年にわたりほぼ無給で手伝い、結果被相続人の財産形成に格別の貢献をした場合や、病気で寝たきりとなっていた被相続人の療養看護を無償で長年にわたり献身的に行ってきた場合などに、その貢献をした相続人の相続分を加算するという制度になります。なお、寄与として認められるのは被相続人の生前に行った行為です。被相続人の死後に葬儀・法要等の実施で貢献した場合などは、寄与として認められません。
(イ)寄与分が認められるための用件
寄与分が認められるためには、相続人自らの寄与があること、その寄与が「特別の寄与」であること、寄与によって被相続人の遺産が維持又は増加したことの要件全てを満たさなければなりません。
以下で詳しく解説します。
① 相続人自らの寄与があること
寄与は原則として相続人自ら行う必要があります。したがって、相続人ではない親族や、被相続人の友人・知人などが寄与を行っても、寄与分は認められません。もっとも、相続人の子や妻(子や妻は相続人ではない)が行った寄与を、相続人自身の寄与行為とみなして、寄与分が認められる場合があります。
例えば、単身赴任中の相続人に代わって、その妻と長女が交代で重度の認知症となった被相続人の介護を不眠不休に近い状態で行い、財産を維持(財産の減少を防止)した場合などは、相続人ではない妻と長女が行った寄与行為を、相続人自身の寄与行為とみなして寄与分が認められる可能性があります。
② その寄与が「特別の寄与」であること
「特別の寄与」とは、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超えた貢献であると解されています。寄与分を主張する相続人は、自分の寄与が「特別の寄与」にあたることを具体的に主張・立証する責任を負います。以下では、寄与行為の主な態様ごとに具体的な判断基準について解説します。
a 家業従事型
被相続人が自営業等を営んでいた場合、その仕事に従事していたことによって寄与分が認められることがあります。具体的には、(1)特別の貢献、(2)無償性(被相続人から対価を貰っていない)、(3)継続性(一時的ではなく、一定の期間従事していた)、(4)専従性(片手間ではなくかなりの労力を費やしていた)の各要件を検討して寄与分の有無を判断します。したがって、例えば親の会社に勤めて普通に給料を貰っていただけという場合は、無償性の要件を満たしませんので、寄与分が認められる可能性は低いと言えます。
b 金銭等出資型
被相続人の事業に関して財産的な給付をした場合等に寄与分が認められることがあります。具体例としては、不動産の購入資金の援助、医療費や施設入所費の負担などです。財産を給付するだけですので、継続性や専従性の要件は必要ありません。
c 療養看護型
相続人が病気で療養している被相続人の療養看護を行ったという場合に寄与分が認められることがあります。具体的には、(1)療養看護の必要性、(2)特別の貢献、(3)無償性、(4)継続性、(5)専従性の各要件を検討して寄与分の有無を判断します。被相続人が療養看護を必要とするだけの病気にかかっていることが前提となりますので、単に被相続人と同居し家事の面倒を見ていただけという場合には、寄与分が認められる可能性は低いと言えます。
d 扶養型
相続人が被相続人を扶養し、生活費等の面倒を見た結果、被相続人の財産が維持された場合に寄与分が認められることがあります。具体的には、(1)扶養の必要性、(2)特別の貢献、(3)無償性、(4)継続性の各要件を検討して寄与分の有無を判断します。親と同居して衣食住の面倒を見ていたとか、別居している親に毎月仕送りしていたという場合に問題となることが多いと言えます。
e 財産管理型
被相続人の財産を管理し、財産の維持形成に寄与した場合に寄与分が認められることがあります。具体的には、(1)財産管理の必要性、(2)特別の貢献、(3)無償性、(4)継続性の各要件を検討して寄与分の有無を判断します。典型例としては、親が所有している不動産の賃貸管理を行った場合などが挙げられます。
③ 寄与によって被相続人の遺産が維持又は増加したこと
寄与分が認められるためには、相続人の寄与行為と遺産の維持・増加の間に因果関係があることが必要です。簡単に言うと、相続人の寄与行為が無ければ、被相続人の遺産はこんなに増えていない、あるいはもっと減っていただろうと認められる必要があるということです。
例えば、家業従事型では相続人の寄与行為により、被相続人の事業が順調に拡大し、被相続人の財産増加に貢献したという場合などであり、療養看護型では、相続人が自宅で献身的に介護した結果、ヘルパー代や施設費がかからず、被相続人の財産の減少が阻止されたという場合などです。
したがって、相続人の寄与行為が被相続人の遺産の維持・増加にとって関係ない場合や、財産上の効果が認められない精神的な援助・協力などの場合は、寄与として認められないことになります。
(ウ)寄与分を定める処分調停
遺産分割に当たって、共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には、法定相続分の他に寄与分が認められますが、寄与分について相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、寄与分を定める処分調停事件として申し立てます。
調停手続では、調停委員が、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらった上で、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指した話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続が開始されますが、遺産分割審判の申立てをしないと不適法として却下されることになります。
(エ)寄与分の立証
寄与分が認められると、遺産から寄与分の額をいわば先取りすることが可能になるので、寄与分の裏付けとなる資料は、誰が見ても納得できる客観的なものを提出する必要があります。具体的には、先程説明した寄与行為の態様に応じて、各要件を立証するための証拠を集めることになります。
例えば、療養看護型の場合は、どの程度の介護行為等を、いつからいつまで行ったのか、被相続人はその当時介護を必要とする状態だったか、要介護認定の有無・程度、働きながら介護していた場合は介護にどの程度の時間を割いていたのか等について証拠を集めて、詳細に主張する必要があります。客観的な証拠の裏付けが無く、大雑把に被相続人の面倒を献身的に見ていたと主張するだけでは裁判所に寄与分を認めてもらうのは困難です。
寄与分を立証するための証拠集めと主張の仕方については、法律の専門知識が不可欠ですので、事前に弁護士とよく相談することをおすすめします。
エ 特別受益や寄与分の主張制限について
相続開始から10年を経過した後にする遺産分割では、特別受益や寄与分の主張ができなくなります(民法第904条の3柱書)。
この民法の規定は、令和3年の民法改正で新設され、令和5年4月1日より施行されています。
特別受益や寄与分を主張したいけれども、相続開始から10年を経過するまでに遺産分割協議がまとまりそうにないという場合は、相続開始から10年を経過するまでに相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をすることで、引き続き特別受益や寄与分を主張することが可能です(同条第1号)。
また、例外的なケースとして、相続開始から10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由(被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかった場合など)が相続人にあった場合において、当該事由が消滅した時から6か月が経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求した場合にも、引き続き特別受益や寄与分を主張することが可能です(同条第2号)。
上記ルールには経過措置が設けられており、令和10年3月31日までは適用が猶予されることになっています。そのため、相続開始から10年が経過した場合でも、令和10年3月31日までであれば、特別受益や寄与分を主張することは可能です。
たとえば平成28年4月1日に相続が開始し、令和8年6月1日に遺産分割を行おうとする場合、令和8年6月1日時点では、相続開始日より10年が経過していますが、改正法施行から5年が経過する前ですので、民法904条の3の規定による期間制限は適用されず、特別受益や寄与分を反映した具体的相続分による遺産分割を求めることができます。
⑸ 相続税申告の問題
相続人が一定額以上の遺産を相続する場合には、相続税の申告義務が生じます。
遺産分割には期限がありませんが、相続税は相続開始があったことを相続人が知った日から10か月以内に申告しなければならず、申告期限を徒過した場合、税額軽減制度や特例制度を利用することができなくなったり、加算税や延滞税が課されることにより、税負担が大きくなったりする可能性があります。そのため、通常相続税の申告期限までに遺産分割を行う必要があります。
ただし、相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わない場合は、暫定的に法定相続分で相続した場合の相続税申告を行い、遺産分割後に相続税の修正申告をすることもできます。
6 遺産分割協議のポイント
⑴ 遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人の遺産をどのように分けるか決定するための相続人全員による話し合いをいいます。遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成すれば遺産分割協議書の内容に基づいて相続手続きをすることができます。
以下では、遺産分割協議の重要なポイントについて詳しく解説します。
⑵ 遺産分割協議が必要なケース
ア 遺言があるが、遺産の分割方法に関する指定が不明確な場合
例えば遺言に「長男に○○を相続させる」と記載されていても、それ以外の遺産の分割方法について具体的な指定がない場合は、残りの遺産の分割方法について相続人間で協議を行う必要があります。
イ 遺言があっても、相続人全員が異なる分割方法を希望する場合
相続人全員が遺言と異なる分割方法を希望する場合、相続人間で分割方法を決めることも可能です。
ウ 遺言書がない場合または遺言書があっても無効である場合
遺言による分割ができないため、相続人間で分割方法について協議を行う必要があります。
⑶ 一部分割の可否について
遺産の一部についてだけの分割協議をすることは可能です。たとえば、以下のような場合に一部分割を行うことがあります。
① 遺産が多岐にわたっていたり相続人が多数いたりして、遺産の全部について一度に分割しようとすると非常に長期の協議が予想されるため、遺産の一部だけを先に分割したいという場合
② 相続税の納付のために必要な財産だけを先に分割したいというような場合
③ 遺産分割協議の際には判明しなかった遺産が後になって発見され、先になされた遺産分割が結果的に遺産の一部だけの分割になる場合
ただし、遺産の残部を分割する場面は将来必ず訪れます。その残部の分割をするときに何らかの不都合が生じることが予測される場合には、遺産の一部だけの分割は控えるのが望ましいでしょう。たとえば、遺産のうち、預貯金のみを先に一部分割して、後に不動産を残部分割するという場合には、不動産の個数や不動産の評価との関係で、各相続人の過不足分を預貯金によって調整する必要が出てくる可能性が高いと考えられますので、一部分割はふさわしくないといえるでしょう。
⑷ 法定相続分と異なる遺産分割を行うことの可否
民法では相続人が誰になるかに応じて、法定相続分という一定の割合が規定されており、法定相続分は、遺産分割協議を行う際の一つの基準や目安となります。
では、遺産分割協議を行う際、この法定相続分にぴったり沿った分割内容でなければならないのでしょうか。
① プラスの財産について
遺産のうち、プラスの財産(積極財産と呼ばれます。)については、相続人全員の合意があれば、各相続人の法定相続分を無視した遺産分割協議をすることが可能です。
遺産分割は、被相続人が死亡した後、相続人全員の共有状態になった遺産をどのように分配するかを決定する手続ですから、共有している相続人全員が、ある分け方に納得して合意するのであれば、どのような分割方法でも認められると考えられているからです。
② マイナスの財産について
他方、遺産のうち、借入金等のマイナスの財産(消極財産と呼ばれます。)については、相続人同士の関係だけではなく、債権者という利害関係者がいることに注意が必要です。
債権者からみれば、自身の知らないところで相続人間の協議が行われた結果、返済能力の乏しい相続人を債務の承継者と決められてしまっては、返済が受けられなくなってしまう等の不都合が生じます。
そのため、借入金等のマイナスの財産のうち、可分な債務(金銭債務等)については、相続開始によって各相続人に法定相続分に応じて当然に分割されて承継されると考えられています。このような可分な債務について、法定相続割合と異なる負担割合を相続人間の協議で決定したとしても、債権者の承諾がない限り、債権者との関係では法定相続分に応じた債務を負うことになります。
不可分な債務(数人の共有者がその共有物を譲渡した場合における所有権移転登記をする義務や目的物を引き渡す義務など)については、相続開始と同時に共同相続人の全員に帰属するため、各相続人が当該債務の全部について責任を負います。債権者は、共同相続人の誰に対しても債務全体の履行を請求することができ、請求を受けた相続人は、債務全体について履行の責任を負うことになります。
⑸ 遺産分割協議書を作成することの重要性
遺産分割協議の方式は自由ではありますが、遺産分割の協議が整った場合には、適切な遺産分割協議書を作成することがとても大事です。
不動産について登記名義の変更をする際など、遺産の名義変更をするために、遺産分割協議書が必要な場合があります。
また、時間が経っても揉めごとが蒸し返されないように、遺産分割協議書を作成して保管しておくことが大事です。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印が必要です。実務では、実印で捺印し、印鑑登録証明書を添付することとしています。
インターネット等で遺産分割協議書のサンプルを入手することができますが、せっかく遺産分割協議書を作っておいても、不備があったり漏れがあったりすれば、またしても揉めごとが起こってしまうことも考えられます。
遺産分割協議書の作成にあたっては、個々の相続によって注意する点が異なり、専門的な知識が必要となりますので、相続に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
⑹ 生前協定について
被相続人の生前に、相続人となることが予定されている者(推定相続人といいます。)の間で、事実上の遺産分割協議が行われる場合があります。生前協定とも呼ばれます。
例えば、高齢の資産家が、遺言書を作成しないまま重度の認知症等になり、遺言書を作成する判断能力を失ってしまった場合を想定します。
このような場合、被相続人による生前の財産処分や遺言書の作成ができなくなるため、推定相続人の間で、被相続人の死後の遺産分けをあらかじめ取り決めて生前協定をしておくことがあります。
生前協定の時点では、分割の対象とした財産は被相続人の所有財産であって、相続発生前にその内容が変動する可能性があります。また、被相続人が死亡する前の時点では、誰が相続人となるかということは確定していません。
そのため、生前協定には法律上の効力・拘束力はありません。生前協定は、単なる紳士協定として、相続紛争の防止を期待する程度の効果を有するに過ぎないのです。
⑺ 遺産分割協議のやり直し
遺産分割協議は、一度成立した場合には、後になってもう一度やり直すことは原則としてできません。例外的にやり直す必要があったり、やり直すことができるのは、以下のような場合が考えられます。
① 遺産分割協議の時、相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫等があった場合
たとえば、一部の相続人が騙されていた場合(詐欺)や、署名捺印を強圧的に無理矢理させられたような場合(強迫)には、成立した遺産分割協議を取り消すことができます。
また、自分に大部分の遺産を相続させる遺言があったにもかかわらず、その遺言を知らずに法定相続分による遺産分割協議に応じてしまったような場合には、錯誤により遺産分割協議を取り消すことが可能になります。
② 相続人の一部が漏れていた場合や、本来相続人でない人が参加していた場合
このような場合は、遺産分割協議が無効になります。
③ 重要な遺産が後になって発見された場合
重要な遺産が漏れていた場合には、錯誤があるとして分割協議の一部または全部を取り消すことが可能になる場合があります。
④ 相続人全員がやり直しに合意した場合
相続人全員の合意があれば、一度成立した遺産分割協議を撤回することもできますし、一部を変更することもできます。
ただし、全員の合意が必要になるため、多大な労力がかかることが多いといえます。また、合意解除や再分割をした場合に、税務上、分割後の贈与であると 認定されて贈与税が課される可能性もあるため、再分割には慎重な配慮が必要です。
⑻ 遺産分割協議を弁護士に依頼した方が良いケース
ア 相続人が多いケース
相続人が多いケースでは、相続人にさらに相続が発生するなどして(数次相続)、相続関係が複雑になる場合が多いため、大量の戸籍を取得した上で、取得した戸籍を正確に読み解いて相続人を確定させる必要があります。一部の相続人が欠けた遺産分割協議は無効となるため、相続人調査は慎重に行わなければなりません。
また、相続人全員が集まって話し合うことが非常に困難であり、話し合いができたとしても、結局折り合いがつかず難航する可能性が高いです。
特に、相続人が10名以上も存在するようなケースでは、被相続人との関係性が希薄であり相続手続に消極的である相続人が多く、そのような相続人は自身の相続分相当額の代償金の支払を受けることを希望する傾向が強いです。他方、被相続人との関係性が深い相続人は被相続人の生前に生活の面倒を看てきたにもかかわらず、不動産や株式などの遺産を取得しなければならず十分な金員を取得することができない場合もあります。
弁護士に依頼することによって、煩雑な相続人調査を弁護士に一任できるだけでなく、感情的な対立や確執がある相続人がいる場合でも、弁護士が代理人となって相続人同士の直接の話し合いを避けることができ、心理的な負担を軽減することができます。
イ 遺産の金額が大きいケース
遺産の金額が大きいほど、各相続人の取り分に対する期待も大きくなるため、遺産の分割方法をめぐって相続人間で意見が食い違いやすく、感情的な対立に発展する可能性があります。
特に遺産額が1億円を超えるようなケースでは、預貯金だけでなく不動産や被相続人が経営していた会社の株式が遺産に含まれる場合が多く、相続人間で争いが生じる可能性が高いです。
弁護士が代理人になることによって、法的に不利な内容で遺産分割をしてしまうことを予防し、適切な内容での遺産分割協議を実現することができます。
ウ 遺産(不動産、株式など)の評価額に争いがあるケース
不動産や株式などの評価が難しい遺産については、相続人間で評価額について意見が合わず、争いになる可能性があります。
不動産は法定相続分で共有することになると、相続人が共有し続けることにより、当該不動産の管理や売却時にトラブルとなったり、共有者が死亡した場合にその相続人との間でもトラブルとなったりすることも多いです。そのため、特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に対し代償金を支払うという代償分割がなされることも多いですが、代償分割は当該不動産の評価額について相続人間で協議が調わずに紛争が長期化するケースが多いです。
遺産(不動産、株式など)の評価額について争いが生じる可能性がある相続の場合には、遺産分割協議を弁護士に依頼し、不動産鑑定や株価鑑定などにより適切な価格を算出した上で、他の相続人と交渉してもらうことによって、遺産分割協議を円滑に進めることができます。
エ 特別受益を主張したい場合
特別受益を主張する者は、その相続人に特別受益があった事実を立証する責任を負い、立証できなければ特別受益は認められません。受益の時期、金額、内容を具体的に明らかにして、それを裏付ける証拠を提出しなければなりません。
特別受益の立証や証拠の収集方法については、相当に専門的な知識・経験を必要とすることが多く、証拠の収集のために、弁護士の職権による調査を行う必要が生じる場合も多々あります。
そのため、特別受益を主張する場合には、相続に強い弁護士への相談をおすすめします。
オ 寄与分を主張したい場合
寄与分を主張する相続人は、自分の寄与が「特別の寄与」にあたることを立証する責任を負い、立証できなければ寄与分は認められません。寄与の具体的内容、時期、寄与によって生じた効果等を具体的に明らかにして、それを裏付ける証拠を提出しなければなりません。
寄与分の立証や証拠の収集方法については、相当に専門的な知識・経験を必要とすることが多く、証拠の収集のために、弁護士の職権による調査を行う必要が生じる場合も多々あります。
そのため、寄与分を主張する場合には、相続に強い弁護士へ依頼することが望ましいといえます。
カ 使途不明金がある場合
使途不明金は、たとえば相続人の一部の者が、被相続人名義の口座から金銭を引き出してその使途が不明のものをいいます。
使途不明金が問題となるケースでは、不当な使い込みの疑いがある相続人に対して、引出しの有無を確認し、引出しを認めた場合には、引出した資金の使途を追及した上で資金の返還を求めたり、あるいは分割方法を調整したりする形で解決を図ります。
もっとも、現実には被相続人の口座からの引出しを認めないケースも多く、相続人同士での話し合いでは解決が困難な可能性もあります。
弁護士に依頼することによって、金融機関の取引履歴、医療・介護記録などの証拠を収集して使い込みの疑いがある相続人との交渉まで一任することができます。
7 遺産分割調停のポイント
⑴ 遺産分割調停とは
遺産分割調停は、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所を通じて行われる手続きです。家庭裁判所の調停委員が中立的な立場で当事者の意見を聞きながら、解決案を提示することによって、相続人間の対立を解消し、合意の成立を促します。調停が成立すると、合意内容に基づいて遺産分割が行われます。
以下では、遺産分割調停について詳しく解説します。
⑵ 遺産分割調停の流れ
ア 申立て
相続人の1人または複数人が他の相続人全員を相手方として、相手方の住所地または当事者が合意で定める地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
申立ての際の、標準的な必要書類は以下のとおりです(相続関係等により、他にも必要となる書類がある場合があります)。
① 遺産分割調停申立書
② 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
③ 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
④ 相続人全員の戸籍謄本
⑤ 相続人全員の住民票または戸籍の附票
⑥ 相続関係図
⑦ 遺産目録
⑧ 遺産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書又は名寄帳、預貯金通帳の写し又は残高証明書、証券会社発行にかかる取引残高報告書、有価証券写し等)
⑨ 特別受益や寄与分を主張する場合はその裏付け資料
イ 調停期日
遺産分割調停申立書が受理されると、家庭裁判所から調停期日が指定され、申立人及び相手側双方が調停期日に裁判所に集まり調停を行います。
調停期日は1か月に1回程度の頻度で開催され、当日は、基本的には当事者間で話し合うことはなく、申立人と相手側が交互に調停室で調停委員と話し合いをします。一方が話し合いをしているときは他方の人は別室で待機することになります。
遺産分割に関して専門的な知識を有している調停委員が、中立的な立場で当事者の意見を聞き、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
ウ 調停手続の終了
① 調停の成立
調停において相続人間で合意が成立すると、その内容を調停調書にまとめることによって、調停が成立します。調停調書の正本または謄本を利用して不動産の名義変更や預貯金の解約をすることができるようになります。また、調停調書は確定判決と同一の効力がありますので、調停調書の内容に従わない相続人がいれば強制的に調停内容の実現をすることができます。
② 調停の不成立
調停において相続人間で合意が成立しない場合、調停は不成立となり、遺産分割審判に移行して、訴訟のように各当事者からの主張や提出された証拠資料などに基づいて裁判官が遺産の分割方法を決定します。
③ 遺産分割調停申立ての取下げ
申立人は、調停の成立又は不成立までの間に、いつでも調停の取下げをすることができます。特段の理由も不要で、相手方の同意も不要とされています。実務上は、取下書を裁判所に提出することとされています。
④ 調停に代わる審判
調停に代わる審判とは、裁判所が、遺産分割調停が成立しない場合において相当と認めるときに、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(調停に代わる審判)をする制度です。遺産分割の合理的な解決や早期の解決を行うために活用されます。たとえば、以下のような場合に用いられることが多いです。
a 遺産分割調停において相続人の大半は遺産分割の方針について同意し協力的であるのに、ただ1人の相続人が方針に反対し、さらにその反対の理由も感情的で全く説得力が無いものであるという場合
b わずかな意見の食い違い等によって遺産分割調停があと一歩のところで成立しない場合
c 相続分が極めて少ない相続人が、遠方の家庭裁判所への出頭に消極的で、調停の呼び出しに応じない場合
d 遺産分割の内容については全相続人が事実上同意しているにもかかわらず、代襲相続などで当事者が多数となっており、各相続人の体調や仕事の都合で、調停期日への全員の出頭確保が難しい場合
ただし、調停に代わる審判が告知された場合でも、審判の告知を受けた日から2週間以内に当事者の誰かが異議を申し立てた場合は、「調停に代わる審判」は効力を失い、遺産分割審判に移行することになります。
⑶ 遺産分割調停のメリット・デメリット
ア 遺産分割調停のメリット
① 冷静な話し合いができる
相続人間で行われる遺産分割協議では、お互いの認識の違いや感情の行き違いでトラブルになることが多くあります。
調停では当事者同士が直接顔を合わせることなく、調停委員を介して話し合いが進みますので、互いに相手の立場を理解しながら、冷静に話し合うことができます。
② 公平な解決ができる
調停では、調停委員や裁判官が公正・中立的な立場で解決策の提案をします。
また、お互いが納得する方向に調整してくれますので、法律的にも公平で円満な解決を目指すことができます。
③ 遺産分割協議に非協力的な相続人がいても解決ができる
相続分が少ない、遠方であるなどといった理由で、遺産分割協議の話し合いに全く応じない相続人がいる場合であっても、調停に代わる審判を利用するなどして解決に導くことができます。
イ 遺産分割調停のデメリット
① 時間がかかる
調停期日は、1か月に1回程度のペースで開かれ、最低でも4~5回程度行われるのが一般的です。結果がまとまるまで1年以上かかるのが通常で、場合よっては2年以上かかることもあります。
また、相続人の範囲や、遺産の範囲などの遺産分割の前提問題に争いがある場合には、調停手続を進めることができず、別途、地方裁判所に民事訴訟を提起して先行して解決しなければならない場合があります。そのような場合にはもっと時間がかかることになります。
② 自分の主張がすべて通るわけではない
調停は、裁判官や調停委員が、当事者全員から意見を聞き、全員が納得する解決を図る手続きですので、必ずしも希望通りの調停結果になるとは限りません。
裁判官や調停委員から説得され、譲歩の上、調停結果を受け入れる必要がある場合もあります。
③ 裁判所へ出向く必要がある
相続人は、調停期日の度に、家庭裁判所へ出向く必要があります。
調停が開かれる回数は1か月に1回ほどですが、調停期日は平日の午前10時~午後5時の間にしか開かれません。このため、会社員の方などにとっては月に1回裁判所に行く時間を作るのも難しい側面があります。
⑷ 遺産分割調停を弁護士に依頼した方が良いケース
ア 煩雑な申立の手続を依頼したい場合
遺産分割調停の申立てを弁護士に依頼すれば、家庭裁判所への申立て手続きをすべて一任することができます。
遺産分割調停の申立てには、戸籍謄本、住民票や固定資産税評価証明書などの様々な必要書類の提出が必要となります。また、申立書への記入や、遺産目録、相続関係図の作成など、煩雑で時間がかかり、また、誤記などがあると、家庭裁判所から訂正を求められることもあります。
弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続や時間を省くことが可能になります。
イ 自分の立場に立って、主張を代弁して欲しい場合
裁判官や調停委員は、あくまで中立的な立場で調停手続を進めます。
したがって、自分に有利となる主張を的確に他の相続人や調停委員、裁判官に伝えたいという場合には、相続に強い弁護士を代理人に立てて、自分の主張を代弁してもらうことが有効です。
また、相続に強い弁護士がついていると、調停委員も一目置くことになります。弁護士が法律的な根拠に基づいた主張をすることにより、調停委員を説得することができ、結果として遺産分割の話し合いを自分に有利に進めることができます。
ウ 調停期日に出席できない場合
調停期日は、平日の午前10時から午後5時の間に開かれます。体調不良や仕事を休むことができず調停期日に出席できない場合でも、弁護士が代理人として調停期日に出席しますので、裁判官や調停委員とやりとりをすることができ、欠席により自分の言いたいことが言えないといった事態を避けることができます。
エ 遺産分割調停を早期に解決したい場合
弁護士であれば、必要な主張やその裏付け資料を調停の場に早期に的確に提出することができ、また、その法律的な知識や経験から、早い段階でお互いの主張の妥協点を見極めることができますので、弁護士が関与した場合の方が、相続人本人が参加する調停に比べ、早期に解決できる傾向があります。
8 遺産分割審判のポイント
⑴ 遺産分割審判とは
遺産分割調停が不成立になった場合には、遺産分割の審判へ移行し、裁判官(家事審判官)が遺産の分割方法を決定することになります。なお、調停が不成立で終了した場合には、当然に審判手続に移行することとされていますので、別途家庭裁判所に審判の申立てをする必要はありません。
遺産分割審判では、遺産の評価、特別受益、寄与分等、相続人間で争われている点について、証拠に基づいて確定的に判断してもらえますので、協議が合意に至らなかったとしても、最終的な解決を図ることができます。
⑵ 遺産分割審判の流れ
ア 調停不成立後、第1回審判期日まで
遺産分割調停が不成立になると、そのまま遺産分割審判に移行することになります。
遺産分割審判に移行すると、遺産分割審判の第1回期日が設定されます。
遺産分割審判は、裁判所が主導的な立場で当事者に主張や立証をさせていくという職権探知主義ですから、当事者の主張・立証が調停の段階で出尽くしているなら、調停が不成立となった後に、別途当事者の主張を聞く期日を設けることなく、これまでの主張・立証に基づいて裁判官が審判を下すことも可能です(家事事件手続法73条1項)。
ただ、通常は、審判を下すには足りない資料などがある場合や、当事者が新たな主張をする機会を与える趣旨で、当事者が出頭する審判期日を指定します。
なお、実務では、調停不成立が決まった最終の調停期日において、裁判官から当事者全員に対して、審判を下すために裁判所が必要と考える資料を提出するよう指示すると同時に、調停段階で明らかになった争点の内容を確認します。
そして、もしもさらに主張があるなら、指定された期日までに提出するよう指示されます。
イ 第1回審判期日から審理終結まで
当事者の出頭のもと、調停不成立以後に提出された主張や証拠があれば、裁判官がこれを確認します。そのうえで、主張・証拠が全部提出されていることを確認し、審理を終結して(家事事件手続法71条)、審判を下す日(審判日)を指定します(同72条)。
審理が終結された後は、もはや主張や証拠の提出は許されません。
第1回審判期日で審判が終わらなければ(通常は1回では終わりません)、次回以降の審判期日を決めたうえ、遺産分割審判が継続していきます。各審判期日は、約1か月から1か月半程度の間隔ごとに入ることが多いです。
なお、事案によっては、当事者が裁判官の前で主張や意見を陳述する「審問」を実施するケースがあり(同68条)、その場合は事前に「陳述書」の提出が求められます。
さらに必要があれば、事実調査のひとつとして、証人尋問や鑑定が実施されることもあります。
これらの手続を実施するための期日が必要であれば、別途そのための審判期日を指定し、これらの実施を終え、もはや必要な事実調査は尽くしたことを確認したうえで、審理を終結し、審判日を指定することになります。
ウ 審判前の話し合いによる解決
審判手続きの過程において、深刻な争点となっていた事項について裁判所の心証が示されるなど、話し合いによる解決の余地が生じる場合があります。そのようなとき、家庭裁判所は、いつでも遺産分割調停に審理の場を移すことができます。この段階で調停が成立すれば、調停調書を作成することにより事件は解決となります。
エ 審判の効力
審判日に審判が下されると、家庭裁判所から各相続人に審判書が送達され、送達の翌日から起算して2週間が経過すると審判内容が確定し(同86条1項)、裁判所で確定証明書を入手することができるようになります。
各相続人は、この審判書と確定証明によって、相続手続(不動産の相続登記、預貯金の解約、払戻し等)を行うことができます。
なお、家庭裁判所は、審判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができます(同196条)。この給付命令には、強制執行の根拠となる債務名義としての効力があります(同75条)。したがって、給付命令に従わない相続人がいる場合には、強制執行によって審判の内容を実現することが可能です。
オ 審判に不服がある場合
審判内容に不服がある場合には、審判の告知を受けた日(審判書の送達を受けた日)の翌日から起算して2週間以内に、高等裁判所に対して「即時抗告」を行わなければなりません(同86条)。
抗告状は、審判をした家庭裁判所に提出します(同87条1項)。
⑶ 遺産分割審判のメリット・デメリット
ア 遺産分割審判のメリット
① 裁判官の判断による客観的かつ公正な解決が図れる
遺産分割審判は、遺産分割協議も遺産分割調停も決裂した後に行われることが基本です。話し合いではどうしても解決できない状態を打破できるというメリットがあります。
そして、審判は、家庭裁判所の裁判官が、当事者の主張、立証を考慮して、また職権で事実調査や証拠調べを行った上で、法に従った客観的かつ公正な判断に基づき下すものですから、最後まで合意の成立に反対していた相続人も納得する可能性もあります。
② 審判に納得のいかない相続人がいても強制執行が可能
審判は、確定した判決と同一の効力を有しますので、審判書に記載されている遺産分割方法を守らない相続人が出たら、強制執行も可能です。
例えば、占有している建物を明け渡すよう命じられた審判に従わない相続人に対しては、建物明渡の強制執行を行い、強制的に立ち退かせることができます。
イ 遺産分割調停のデメリット
① 時間がかかる
遺産分割審判は、遺産分割協議及び遺産分割調停による話し合いによっても相続人の合意が得られない場合の終局的な解決方法となるため、調停手続よりさらに時間を要します。
家庭裁判所の審判に異議が申し立てられたら、さらに時間がかかることになります。
② 法定相続分による分割となりやすい
審判は法律に従って分割方法を決定するため、相続人それぞれの事情をすべて考慮するのは難しいケースもあります。法定相続分以上の主張を行っても、 受け取れる財産額を増やすのは難しいです。
寄与分や特別受益なども証拠がなければ認められないため、ハードルが高く、結果として法定相続分による分割となる場合が多いです。
③ 葬儀費用、負債等の問題は扱えない可能性が高い
遺産分割協議や遺産分割調停では、相続人が合意すれば、幅広く相続に関する問題を扱うことが認められますが、審判手続きの場合、審理の対象が限定されます。
例えば、葬儀費用の負担や被相続人の借入金の負担の問題、祭祀承継の問題(お墓を誰が管理するかなど)は、審判の対象としてもらうことができず、別途、民事訴訟等で解決する必要があります。
④ 不動産の売却が審判の結果として行われる可能性がある
不動産の公正な評価や相続人間の利益均等化を図るため、審判においては、不動産について競売による換価分割が採用される場合があります。
一部の相続人が不動産を残したいと希望しても、その相続人が代償金を支払える資力がないと判断された場合、不動産を競売して現金化し、相続人に分配することを命じる可能性があります。
⑷ 遺産分割審判は弁護士に任せるべき理由
遺産分割協議や遺産分割調停は、あくまで相続人間の合意による解決を目指すものですので、弁護士に依頼せずに相続人本人が手続を進めても、予期せぬ結果となることは少ないものと思われます。
しかし、遺産分割審判は、当事者の主張立証を考慮しながらも、最終的には裁判所が法に従って判断をしますので、主張立証すべきことが不完全であった場合には、予期せず不利な審判が下される危険性があります。
また、遺産分割審判における審理事項は、特別受益や寄与分といった高度な法的判断が必要なものであり、特別受益や寄与分を裏付ける証拠も的確なものを提出していく必要があります。
希望する遺産分割方法についても、裁判官を説得させるに足りる合理的な根拠に基づく主張を行う必要があり、これが不十分であると、取得を希望する不動産について取得できないばかりか、競売を命じられる危険性もあります。
したがって、納得のいく審判を求めるのであれば、遺産分割審判においては、相続や訴訟に強い弁護士に依頼して、自らに有利な主張及び立証を尽くしてもらう必要があるでしょう。
9 遺産分割を弁護士に依頼するメリット
このように遺産分割は、相続人同士の話し合いが必要不可欠である一方で、親族間の感情的な対立が生じやすい場面でもあります。ここで改めて、弁護士に依頼することで得られる代表的なメリットをご紹介します。
⑴ 適切な遺産配分の割合がわかる
遺産分割を進めるうえで重要なのが、相続人一人ひとりがどれだけの遺産を受け取るべきかを正しく理解することです。しかし、実際には「法定相続分」や「特別受益」「寄与分」などの要素が絡み合い、相続人ごとの適切な取り分を正確に把握するのは簡単ではありません。弁護士に依頼することで、依頼者の立場や家庭の事情を踏まえつつ、法的根拠に基づいた遺産配分の指針を明確に示してもらうことができます。
また、財産に不動産が含まれている場合には、現物分割・代償分割・換価分割などの中から、実情に即した最適な分割方法のアドバイスを受けることができます。
さらに、自らが介護や経営などで被相続人に貢献してきた場合には、「寄与分」として相続分の加算を主張することも可能です。こうした複雑な法的主張や証拠整理も、弁護士が的確に対応します。
相続人同士での話し合いでは見落としがちな重要ポイントも、弁護士の視点から整理し、依頼者にとって最も有利な結果を導くことが可能です。
関連記事:「5.遺産分割手続における共通の問題点」
「6.⑻ 遺産分割協議を弁護士に依頼した方が良いケース」
⑵ 調停・審判などの法的手続きに対応できる
遺産分割協議がまとまらない場合、相続人の一方が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。さらに、調停でも解決できない場合には、家庭裁判所による「審判」に進み、裁判所が遺産の分け方を法的に決定します。
こうした裁判所を介する手続きには、法的な主張や証拠の整理、書類の提出、期日の対応など専門的な知識が求められます。不慣れな方が単独で対応するのは困難であり、手続きの遅延や不利な判断を招く可能性もあります。
弁護士に依頼することで、調停では依頼者の代理人として出席し、法的根拠に基づいて主張を整理・代弁します。また、審判においても、適切な証拠資料の収集や、遺産評価・寄与分・特別受益の主張など、依頼者にとって有利な判断を得るための支援が可能です。
さらに、調停委員や裁判官とのやり取りにおいても、弁護士が同席・代弁することで、冷静かつ専門的な対応ができ、精神的な負担も大きく軽減されます。
このように、弁護士のサポートがあれば、調停や審判といった複雑な法的手続きも安心して進めることができます。ご自身やご家族の大切な権利を守るためにも、早い段階からのご相談をおすすめいたします。
関連記事:「7.⑷ 遺産分割調停を弁護士に依頼した方が良いケース」
「8.⑷ 遺産分割審判を弁護士に任せるべき理由」
10 弁護士費用
⑴ 弁護士費用はどれくらい?
遺産分割を弁護士に依頼する際、どのような費用が発生するのか、事前に把握しておくことは非常に重要です。弁護士費用は事務所によって異なりますが、当事務所では以下のとおりです。
① 弁護士費用は多くの場合、着手金と成功報酬金の二本立てとなります。
遺産分割案件(遺産分割示談交渉案件、同調停案件、同審判案件)の弁護士費用は、その案件の経済的利益(案件の規模)によって決まります。
② 遺産分割案件の経済的利益は、「対象となる相続分の時価相当額」です。
ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、「その相続分の時価相当額の3分の1の額」です。
③ 着手金と成功報酬金の算定方法
上記②の経済的利益に下記の料率を乗じたものをそれぞれタテに合算した額が着手金および成功報酬金の標準となります。
| 経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
| 3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
④ 具体的計算例
例えば、ご依頼人の相続分の時価が9000万円で、うち6000万円部分については分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いがなく、残りの3000万円部分については争いがあるというケースであれば、
(1)経済的利益は
6000万円×1/3+3000万円=5000万円
です。
(2)着手金の標準額は(上記3の表を当てはめて)消費税込みで、
240万9000円
(3)成功報酬金の標準額は(上記3の表を当てはめて)消費税込みで、
481万8000円
となります。
⑤ 調停案件、示談交渉案件の場合の減額
調停案件または示談交渉案件の場合は、事案の内容により、上記③④で計算された額の3分の2を下限として減額します。
⑥ 示談から調停または審判手続きに移行する場合の着手金追加について
示談交渉事件を受任し、着手金を標準額の3分の2に減額して220万円(税込)と取り決めた(110万円減額した)ケースを想定します。このケースで、
・示談が成立せず調停手続きに移行した場合は、原則として着手金の追加払いをしていただく必要はありません。
・調停が成立せず審判手続きへ移行する場合は、原則として、上記で減額した110万円を追加払いしていただきます。
⑦ ご依頼人との協議による減額
以上の③~⑤の金額はあくまで標準的な目安であり、個々の案件ごとに複雑性や難易度を考慮し、ご依頼人と協議の上、妥当な範囲で増減する場合があります。
⑵ いつ誰が払う?
遺産分割に関する弁護士費用は、弁護士に依頼をした相続人が支払うのが原則です。
各相続人が個別に依頼する場合はそれぞれが費用を負担するのが当然ですが、複数の相続人が共同して依頼する場合は、あらかじめ相続人間で費用分担の合意を交わしておくことが望ましいでしょう。
遺産分割に関する弁護士費用を支払うタイミングは、通常、以下のとおりです。
・法律相談料 相談時に都度支払い
・着手金 正式に依頼する段階で支払い
・成功報酬金 手続き完了後(協議成立・調停成立・審判確定など)に支払い
・実費、日当 必要に応じて発生都度、またはまとめて支払い
11 まとめ
遺産分割は、相続人同士の関係性や財産の種類・価値によって、想像以上に複雑化することがあります。不動産や預貯金の分け方、相続割合の調整、感情的な対立など、さまざまな問題に直面する中で、「何から手をつければいいのか分からない」と不安を感じている方も少なくありません。そうした不安を放置せず、早い段階で弁護士に相談することが、円満な相続への第一歩です。
弁護士は法律の専門家として、協議の進め方から調停・審判対応、遺言作成や遺産整理まで、依頼者の状況に応じた的確なアドバイスと実務サポートを提供します。
大切な家族の財産を守り、円滑な相続を実現するためにも、ぜひお気軽にご相談ください。