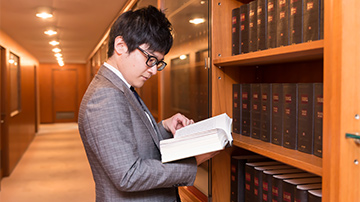相続問題の専門知識
遺産分割
遺産分割について
1. 遺産分割とは
遺言書がない場合、相続の開始とともに、被相続人の遺産は相続人全員が各相続分に基づき暫定的に共有している状態になります。
その共有状態を解消し、各相続人に、どの遺産を、どのように分配するかを具体的に決定することを、遺産分割といいます。
(1) 遺産分割の期限
遺産分割に期限はありません。もっとも、近年、早期の遺産分割を促進する目的で法改正がなされ、遺産分割が遅れた場合には下記のような不利益を被ることとなりました。
ア. 特別受益や寄与分の主張制限(令和5年4月1日施行、ただし令和10年3月31日までは適用が猶予されている)
相続開始から10年を経過した後にする遺産分割では、特別受益(共同相続人が被相続人から受けた遺贈又は婚姻のため、養子縁組のため、若しくは生計の資本としての贈与)や寄与分(被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与)の主張ができなくなります(民法第904条の3柱書)。
特別受益や寄与分を主張したいけれども、相続開始から10年を経過するまでに遺産分割協議がまとまりそうにないという場合は、相続開始から10年を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割を請求することで、引き続き特別受益や寄与分を主張することが可能です(同条第1号)。
また、例外的なケースとして、相続開始から10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由(被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかった場合など)が相続人にあった場合において、当該事由が消滅した時から6か月が経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求した場合にも、引き続き特別受益や寄与分を主張することが可能です(同条第2号)。
上記ルールには経過措置が設けられており、令和10年3月31日までは適用が猶予されることになっています。そのため、相続開始から10年が経過した場合でも、令和10年3月31日までであれば、特別受益や寄与分を主張することは可能です。
イ. 相続登記申請の義務化(令和6年4月1日施行)
相続によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務が課されます(改正不動産登記法第76条の2第1項)。
3年以内に遺産分割協議が成立した場合には、その内容を踏まえた相続登記の申請を行います(同条第1項前段)。
3年以内に遺産分割協議が成立しない場合には、法定相続分での相続登記の申請(同段)又は「相続人申告登記」(相続や遺贈によって登記義務を負った相続人が、登記官に対し、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨、及び、②自らがその相続人である旨の2点を、申請義務の履行期間内に申し出ること)の申出(同法第76条の3第1項)を行います。この場合、分割協議が成立した後、遺産分割協議の成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行います(同法第76条の2第2項)。
「正当な理由」無くして登記申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料が課せられます(同法第164条第1項)。
相続税申告期限との関係
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。相続税の申告・納付が必要な場合には、申告期限内に、納税地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出して相続税を納付しなければなりません。
実務上は、この相続税申告期限を目安に遺産分割がなされることが多いといえますが、これは税法上の期限であって、遺産分割そのものの期限ではありません。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ Q&A法律相談 遺産分割の時期
(2) 遺産分割の禁止
一般的には、遺産分割はできるだけ早期に行うことが望ましいといえます。
ただし、たとえば、一部の相続人の年齢がまだ若く判断力が成熟するのを待ってから遺産分割をさせたいというような場合や、相続開始後すぐの分割を認めてしまうと深刻な相続トラブルが起きることがあらかじめ予測されるような場合等、必ずしも早期に遺産分割を行うべきではない場合もあります。
そのような場合には、遺産分割を一定期間禁止する方法があります。
ア. 遺言による遺産分割の禁止
被相続人は、遺言によって、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部についてその分割を禁止することができます。遺産分割の禁止は、遺言によって行わなければならず、それ以外の生前行為で指定することは認められません。
イ. 家庭裁判所による遺産分割の禁止
遺言によって遺産分割が禁止されている場合ではなくても、特別の事由がある場合には、家庭裁判所は、相続開始後に、遺産の全部又は一部について期間を定めて分割を禁じることが可能です。
ア. 相続人全員の合意による遺産分割の禁止
相続人全員が合意すれば、遺産分割を禁止することは可能です。遺産分割は遺産共有状態を解消するために遺産の分配を決める手続ですから、相続人全員の合意によって、共有状態の解消を先延ばしにすることは構わないからです。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ Q&A法律相談 遺産分割の禁止
(3) 遺産分割前のトラブル
遺言書がない場合、相続の開始とともに、被相続人の遺産は相続人全員が各相続分に基づき暫定的に共有している状態になります。
そのため、遺産の使用・収益・処分の方法について、共有者間で様々な問題が生じ得ます。
ア. 相続人の1人が、遺産分割前の不動産を独占的に使用・収益している場合に、明渡し請求や損害賠償請求をすることの可否
相続人の1人が、他の相続人の同意を得ずに、被相続人の遺産である不動産を独占的に使用、収益するケースはしばしば見受けられます。この場合、他の相続人は、明渡し請求や損害賠償請求をすることができるかという問題があります。
① 明け渡し請求
被相続人の死亡後から遺産分割完了までの間、被相続人が所有していた遺産は、相続人の共有となります。そして、各相続人は、それぞれ共有持分権に基づいて共有物の全部を使用する権限を有しています。そのため、共有持分権を有する他の相続人であっても、遺産である不動産を独占して使用・収益している相続人に対して、当然には明渡しを求めることはできないと考えられています。
② 賃料相当の損害金の請求
もっとも、遺産である不動産を独占している相続人が、自己の相続分に基づく使用収益の範囲を超えて利益を得ている場合については、他の相続人は、不当利得の返還請求や、不法行為による損害賠償請求として、各人の相続分に応じた金銭(賃料相当損害金)の支払を求めることができます。
③ 被相続人の生前から被相続人と同居していた場合
遺産である不動産を独占している相続人が、被相続人の生前から、被相続人とその不動産に同居していたような場合、不動産の所有関係が最終的に確定するまでの間はその相続人に不動産を無償使用させる旨の合意があったと推認されるとして、遺産分割完了までは、他の相続人は、原則として明渡しや損害賠償を求めることはできないという判例があります(最高裁平成8年12月17日判決)。
④ 配偶者短期居住権
上記最高裁平成8年12月17日判決はあるものの、被相続人が明確に異なる意思を表示していた場合等には、配偶者の居住権は短期的にも保護されないことになります。その場合、配偶者は住み慣れた住居を退去しなければならなくなり、とても大きな負担となります。そこで、配偶者には、被相続人の意思にかかわらず、従前居住していた建物に、被相続人の死亡後少なくとも6か月間は引き続き無償で居住することができる権利(配偶者短期居住権)が保障されています(民法第1037条第1項本文)。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ 解決例「事例1 突然、見ず知らずの者に長年住み慣れた自宅から出て行けと言われたケース」
⇀ 解決例「事例2 収益用不動産の取得に折合いがつかなかったケース」
イ. 遺産分割前に、遺産や持分を処分することの可否
遺言書がない場合、相続の開始とともに、被相続人の遺産は相続人全員が暫定的に共同所有している状態になります。
遺産共有状態にある個々の物や権利を遺産分割前に処分しようとする場合には、共有物に関する民法の規定に従うこととなります。
① 遺産の処分
遺産分割前の遺産の処分行為(たとえば売却等)は、原則として、相続人全員の同意のもとに行わなければなりません。そのため、処分行為に反対する相続人が1人でもいる場合には、遺産分割をして当該遺産を取得してから処分行為をすることになります。
② 個々の持ち物の処分
各相続人は、遺産分割前には、遺産に該当する物や権利について、相続分に応じた持分権を有しているものとされます。その持分の限度においては、他の相続人の同意を得ずとも単独で処分することができます。
相続人の1人がその持分を第三者に譲渡した場合、譲渡された持分は、遺産分割の対象から外れます。そのため、持分の譲受人が他の相続人との共有関係を解消することを希望する場合には、遺産分割の手続によるのではなく、共有物分割という手続をとることになります。
こちらもあわせてご覧ください。
相続問題の専門知識 遺産分割審判前の保全処分・調停前の処分
このように、遺産分割自体の期限はありませんが、一定の権利を主張することのできる期限や相続登記の期限が義務化されます。
また、遺産分割が長引くことにより、様々な法的問題を引き起こすリスクがあります。
当事務所では、遺産分割事件に精通した弁護士が、クライアントのご要望に合わせた最適なアドバイスを提供した上で、遺産分割に関するトラブルを未然に防ぎ、円滑かつ迅速な解決をサポートし、遺産分割を的確に進めてまいりますので、お気軽にご相談ください。
2. 遺産分割の手続きと流れ
遺産分割手続は、遺言書がある場合とない場合とで、流れが大きく異なります。
(1) 遺言書による分割(指定分割)
ア. 遺言書による分割とは
遺言書があるかないかによって、遺産分割手続の方法は大きく異なっていきます。
遺言書によって、遺産の分割方法について遺言で具体的に指定されている場合には、相続人間で遺産分割協議を行わなくても、その遺言のとおりに遺産分割をすることができます。
たとえば、遺言書で、ある不動産を誰に相続させるかが具体的に記載されていれば、その遺言書によって、その不動産の登記名義を変更することができます(ただし、自筆で作成された遺言書は、原則として家庭裁判所で検認という手続等を経る必要があります。)。
また、預貯金等の金融資産についても、遺言書に遺言執行者が指定されていれば、相続人全員の署名捺印を揃えなくても、遺言執行者が解約手続や名義変更手続等を行うことができます。
イ. 遺言書の効力について
遺言書が存在する場合は、まずその遺言書の効力に問題が無いかどうかの確認を行います。遺言書の効力が問題となるのは、特に自筆証書遺言のケースが多いでしょう。
① 自筆証明遺言の場合
自筆証書遺言の場合は、まず法律で決められた方式(全文自書、日付・署名の記載、押印)が守られているかどうかを確認する必要があります。仮に方式に不備がある場合は、遺言書そのものが原則として無効となります。
次に、方式に問題が無い場合は、その他に遺言の有効性に問題が無いかどうかを確認します。最も問題となりやすいのは、遺言書を作成した当時、遺言者に「遺言能力」があったかどうかという点です。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ 解決例「事例4 遺言書案をもとに相続分を争ったケース」
② 公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証人が要式に従って遺言作成を行いますので、方式不備により無効となるおそれは基本的に無いといえます。
問題となり得るのは遺言能力の有無ですが、公正証書遺言は公証人の他に、2名の証人が立ち会い、複数の人間で遺言者の意思・判断能力についてその場でチェックを行いますので、遺言能力についても相応の確認が行われます。
そのため、自筆証書遺言と比べて、遺言能力を巡って紛争になる可能性は低いと言えますが、公正証書遺言の場合であっても、遺言能力が争われて遺言書が無効と判断された裁判例もあります。
ウ. 遺言無効を争う場合
遺言の効力を裁判で争う場合には、遺言無効確認の訴えを裁判所に提起します。この場合、遺言の無効を主張する者が、無効を裏付ける資料を提出する責任(これを「立証責任」といいます。)を負います。
遺言の無効理由となるのは、方式の不備、遺言能力の欠如のほか、遺言内容が公序良俗に反している場合も無効となります。このうち、争われることが多いのは、遺言能力の有無です。
遺言能力とは、自身の遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識することができる判断能力をいい、遺言能力がない状態で書かれた遺言は無効となります。たとえば、重度の認知症により自分がどれだけの財産を持っているのか、自分が亡くなったらどう財産を分けたいのかについて認識・判断ができない状態になっている場合には、遺言能力はないものと考えられます。
ただし、遺言書作成当時に遺言能力がなかったことを証明するためには、立証方法や証拠の収集方法について高度に専門的な知識・経験を必要とすることが多いといえます。また、遺言者が当時入院していた病院や施設に対して証拠資料の提出を依頼する場合には、弁護士や裁判所の職権による調査を行う必要が生じる場合も多々あります。
そのため、遺言書の効力を争いたいという場合には、相続に強い弁護士への相談をおすすめします。
エ. 遺言書と異なる遺産分割をすることの可否
① 相続人全員が遺言の存在、内容を知っている場合
被相続人は遺言で、遺産の分け方を基本的に自由に決定することができます(ただし、遺留分を侵害する遺言書の場合には、一部の相続人から遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。)。とはいえ、被相続人が遺言書で決めた遺産の分け方が、相続人からみればあまり望ましくない、という場合もあります。
そのような場合、相続人全員が遺言の内容を知った上で、遺言書とは別の分割方法を合意すれば、遺言書と異なる遺産分割を行うことは可能とされています。
ただし、遺言書で財産を相続人以外の第三者に遺贈することが書かれている場合には、その財産はその第三者のものになります。また、遺言書に遺言執行者の定めがある場合には、通常遺言執行者の同意を得ることが必要とされています。
② 遺言の存在を知らずに遺産分割協議が成立してしまった場合
- 相続人の全員が、遺言書の存在や内容を知らなかったときには、協議の結果が遺言書で決められた内容よりも有利になったり不利になったりする相続人が生じ得ます。不利の程度が大きい場合には、遺産分割協議の一部または全部が錯誤によって無効となる場合があります。
- 一部の相続人が、不当な目的で、遺言書を故意に破棄・隠匿していたような場合には、その相続人は相続開始の時に遡って相続資格を失うことになります(「相続資格の欠格」といいます。)。そのため、遺産分割協議が成立していたとしても、本来相続する資格のない者が遺産分割協議に参加したことになるため、その協議は無効となります。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ Q&A法律相談 遺言と異なる遺産分割協議
(2) 協議分割
ア. 協議分割(遺産分割協議)とは
遺言書がない場合、または、遺言書があっても遺産分割に関する指定が明確でない場合は、原則として、相続人全員で話合い(遺産分割協議)を行って分割方法を決めることになります。相続人の間で協議がまとまれば、遺産を分けることができます。
遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる分割協議をすることも認められます。遺産分割協議は、特別の方式が定められているものではありません。ただし、実務上は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印(通常、実印で捺印します。)し、印鑑登録証明書を添付することとなります。なお、相続人全員で行わなかった遺産分割協議は、無効になりますので、まず相続人の調査・確定をする必要があります。
イ. 一部分割について
遺産の一部についてだけの分割協議をすることは可能です。たとえば、以下のような場合に一部分割を行うことがあります。
- 遺産が多岐にわたっていたり相続人が多数いたりして、遺産の全部について一度に分割しようとすると非常に長期の協議が予想されるため、遺産の一部だけを先に分割したいという場合
- 相続税の納付のために必要な財産だけを先に分割したいというような場合
- 遺産分割協議の際には判明しなかった遺産が後になって発見され、先になされた遺産分割が結果的に遺産の一部だけの分割になる場合
ただし、遺産の残部を分割する場面は将来必ず訪れます。その残部の分割をするときに何らかの不都合が生じることが予測される場合には、遺産の一部だけの分割は控えるのが望ましいでしょう。
たとえば、遺産のうち、預貯金のみを先に一部分割して、後に不動産を残部分割するという場合には、不動産の個数や不動産の評価との関係で、各相続人の過不足分を預貯金によって調整する必要が出てくる可能性が高いと考えられますので、一部分割はふさわしくないといえるでしょう。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ 解決例 「事例23 調停も審判も不可能と思われた事案で一部分割の調停が成立したケース」
ウ. 法定相続分と異なる遺産分割を行うことの可否
民法では相続人が誰になるかに応じて、法定相続分という一定の割合が規定されており、法定相続分は、遺産分割協議を行う際の一つの基準や目安となります。
では、遺産分割協議を行う際、この法定相続分にぴったり沿った分割内容でなければならないのでしょうか。
① プラスの財産
遺産のうち、プラスの財産(積極財産と呼ばれます。)については、相続人全員の合意があれば、各相続人の法定相続分を無視した遺産分割協議をすることが可能です。
遺産分割は、被相続人が死亡した後、相続人全員の共有状態になった遺産をどのように分配するかを決定する手続ですから、共有している相続人全員が、ある分け方に納得して合意するのであれば、どのような分割方法でも認められると考えられているからです。
② マイナスの財産
遺産のうち、債務等のマイナスの財産(消極財産と呼ばれます。)については、相続人同士の関係だけではなく、債権者という利害関係者がいることに注意が必要です。
債権者からみれば、自身の知らないところで相続人間の協議が行われた結果、返済能力の乏しい相続人を債務の承継者と決められてしまっては、返済が受けられなくなってしまう等の不都合が生じます。
そのため、金銭を支払う内容の債務については、相続によって各相続人に法定相続分に応じて当然に分割されて承継されると考えられています。
債務について、法定相続割合と異なる負担割合を相続人間の協議で決定したとしても、債権者の承諾がない限り、債権者との関係では法定相続分に応じた債務を負うことになります。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ Q&A法律相談 法定相続分と異なる遺産分割協議
⇀ 相続問題の専門知識 具体的相続分の算定
エ. 遺産分割協議書を作成することの重要性
遺産分割協議の方式は自由ではありますが、遺産分割の協議が整った場合には、適切な遺産分割協議書を作成することがとても大事です。
- 不動産等の遺産の名義変更をする際には、通常遺産分割協議書が必要です。
- 時間が経っても揉めごとが蒸し返されないように、適切な遺産分割協議書を作成することが大事です。
-
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印が必要です。実務では、実印で捺印し、印鑑登録証明書を添付することとしています。
インターネット等で遺産分割協議書のサンプルを入手することができますが、せっかく遺産分割協議書を作っておいても、不備があったり漏れがあったりすれば、またしても揉めごとが起こってしまうことも考えられます。
遺産分割協議書の作成にあたっては、個々の相続によってそれぞれ事情が異なりますので、相続に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ Q&A法律相談 遺産分割協議書の方式
オ. 生前協定について
被相続人の生前に、相続人となることが予定されている者(推定相続人といいます。)の間で、事実上の遺産分割協議が行われる場合があります。生前協定とも呼ばれます。
例えば、高齢の資産家が、遺言書を作成しないまま重度の認知症等になり、遺言書を作成する判断能力を失ってしまった場合を想定します。
このような場合、被相続人による生前の財産処分や遺言書の作成ができなくなるため、推定相続人の間で、被相続人の死後の遺産分けをあらかじめ取り決めて生前協定をしておくことがあります。
生前協定の時点では、分割の対象とした財産は被相続人の所有財産であって、相続発生前にその内容が変動する可能性があります。また、被相続人が死亡する前の時点では、誰が相続人となるかということは確定していません。
そのため、生前協定には法律上の効力・拘束力はありません。生前協定は、単なる紳士協定として、相続紛争の防止を期待する程度の効果を有するに過ぎないのです。
カ. 遺産分割協議のやり直し
遺産分割協議は、一度成立した場合には、後になってもう一度やり直すことは原則としてできません。やり直す必要があったり、やり直すことができるのは、以下のような場合が考えられます。
① 遺産分割協議の時、相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫等があった場合
たとえば、一部の相続人が騙されていた場合(詐欺)や、署名捺印を強圧的に無理矢理させられたような場合(強迫)です。
また、自分に大部分の遺産を相続させる遺言があったにもかかわらず、その遺言を知らずに法定相続分による遺産分割協議に応じてしまったような場合には、錯誤により無効となる可能性が高いといえます。
② 相続人の一部が漏れていた場合や、本来相続人でない人が参加していた場合
このような場合は、遺産分割協議が無効になります。
③ 重要な遺産が後になって発見された場合
重要な遺産が漏れていた場合には、錯誤により分割協議の一部または全部を無効と主張できる場合があります。
④ 相続人全員がやり直しに合意した場合
相続人全員の合意があれば、一度成立した遺産分割協議を撤回することもできますし、一部を変更することもできます。
ただし、全員の合意が必要になるため、多大な労力がかかることが多いといえます。また、合意解除や再分割をした場合に、税務上、分割後の贈与であると認定されて贈与税が課される可能性もあるため、再分割には慎重な配慮が必要です。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ Q&A法律相談 遺産分割協議のやり直し
キ. 遺産分割協議の債務不履行
遺産分割協議が成立したものの、一部の相続人が協議において決めた約束事を果たさないことがあります。
たとえば、相続人Aが特定の遺産を相続する代わりに、他の相続人Bに対して金銭を支払うという分割方法(代償分割といいます。)を決定したものの、相続人Aが金銭を支払わないという場合等です。
そのような場合でも、債務不履行を理由に分割協議を解除してやり直すことは原則としてできません。別途、民事訴訟で履行や損害賠償を求めたり、強制執行をしたりすることになります。
分割協議書を作成する際に、同時履行条項を設けたり、相当の担保の提供を求めたりして、債務が履行されなかった場合にもスムーズに対処できるようにしておくのが望ましいでしょう。
ク. 裁判で遺産分割の効力を裁判で争う場合(遺産分割不存在確認、無効確認訴訟)
遺産分割協議がされていないのに、遺産分割協議書が偽造されているような場合には、遺産分割協議の不存在確認訴訟を提起することができます。
遺産分割協議に無効原因(相続人が漏れていた、意思無能力の相続人がいた、錯誤があった等)がある場合には、遺産分割協議の無効確認訴訟を提起することができます。
遺産分割協議に取消原因(詐欺、強迫、保佐人や補助人の同意がない場合)がある場合には、取消しの意思表示を行った上で、遺産分割協議の無効確認訴訟を提起することができます。
担保責任による解除が認められる場合にも、解除の意思表示を行った上で、遺産分割協議の無効確認訴訟を提起することができます。
(3) 調停分割(遺産分割調停)
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、そもそも協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停を申立てることができます。
調停を行って相続人間で合意が成立すれば、調停が成立したこととなり、遺産分割調停の手続は終了します。調停が成立すると、確定した審判と同一の効力を有することになり、調停調書をもって直ちに強制執行をすることができます。
ただし、遺産分割調停は裁判所を通じて行いますが、あくまで話合いをする手続です。そのため、調停を行っても、話合いがまとまらなければ、遺産分割調停は不成立となって終了する場合もあります。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ 相続問題の専門知識 遺産分割調停について
⇀ Q&A法律相談 遺産分割協議の不成立
⇀ 解決例 「事例14 遺産の売却配分に難航したケース」
(4) 審判分割(遺産分割審判)
遺産分割調停が不成立となった場合には、遺産分割の審判となり裁判官(家事審判官)が遺産の分割方法を決定し、強制的に遺産を分割することになります。審判分割では、法定相続分を基準とした分割が行われます。
なお、調停が不成立で終了した場合には、当然に審判手続に移行することとされていますので、別途家庭裁判所に審判の申立てをする必要はありません。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ 相続問題の専門知識 遺産分割審判とは
⇀ 解決例 「事例21 調停に代わる審判で解決に導いたケース」
⇀ 解決例 「事例22 相続分の譲渡を受けた後に調停に代わる審判で解決に至ったケース」
3. 相続人の確定
遺産分割は相続人全員で行う必要があるため、その前提として相続人を確定することが不可欠です。
仮に、相続人の中に、行方不明者、未成年、意思能力がない者、胎児、遺産分割後に認知を得た子などがいる事案では、適切な法的手続きを踏まなければ、遺産分割が無効となるリスクもあります。
例えば、行方不明者がいる場合は、行方不明者の所在を調査した上で、不在者財産管理人選任申立てや、失踪宣告などの手続きを行う場合があります。
また、未成年がいる場合には、親権者との遺産分割協議や、特別利害関係人の選任申立てなどの手続きを行う場合もあり、意思能力がない者がいる場合は後見申立てが必要な場合もあります。
いずれにせよ、遺産分割をする上で相続人を確定するためには、様々な法的問題に直面する可能性がありますので、相続問題に精通した弁護士にご相談することをおすすめします。
相続人の確定について詳しくはこちらをご覧ください。
⇀ Q&A法律相談 遺産分割と意思能力
⇀ Q&A法律相談 遺産分割と利益相反
4. 分割すべき遺産の確定
被相続人が相続開始時に有していた権利・義務は、原則としてすべて相続の対象となり、相続人に承継されます。
しかし、相続の対象となるかということと、相続の対象となるとしても遺産分割の対象となるかということとは法的に区別して考えられており、遺産分割の対象となるか否かは、遺産の種別によって様々です(法的には遺産分割の対象に含まれないものの、実務上、相続人全員の合意を得て、遺産分割の対象とすることが多いケースもあります。)。
また、遺産の範囲について相続人間で合意が得られない場合、遺産分割の前に、遺産確認の訴えを提起し、遺産の範囲について確定させなければならない場合もあります。
遺産分割を行う際には、上記の区別を前提に財産の調査を適切に行い、紛争を蒸し返さないよう可能な限り一度の遺産分割で解決することが望ましいとされます。
分割すべき遺産を確定し、遺産の調査を適切に行うことは、遺産分割を円滑に進める上で非常に重要であるため、相続問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ Q&A法律相談 生命保険と遺産分割
5. 遺産の評価
遺産分割の際には、まず、対象となる財産の評価が不可欠です。
遺産の客観的な価値は絶えず変動しており、評価の基準時を決定することが重要です。
具体的な評価方法や基準時に関する問題は、相続人が法定相続分を算定する段階と、その具体的相続分に基づいて遺産を分配する段階で発生します。
特に不動産の評価が相続人間で争いが生じやすく、不動産の評価方法には固定資産税評価額や路線価などの公的基準がありますが、相続人間の合意が得られない場合、時価を評価する必要があります。時価の評価には不動産鑑定が最も信頼できる方法とされていますが、鑑定費用が高額であり、裁判所が鑑定士を選任することが通例です。
不動産の利用権や非上場株式なども評価が必要であり、それぞれの具体的事情に応じて適切な方法で評価する必要があります。
現金や預貯金、上場株式、動産などは通常、金額が明確なので争いになりにくいですが、高価な書画や骨董品については専門家の意見を聞き合意を得ることが一般的です。
いずれにせよ、遺産の評価にあたっては、遺産の種別に応じて専門家による鑑定が必要となり、その鑑定結果を適切に評価した上で、裁判手続などで説得的に主張することが重要です。
6. 遺産分割協議をうまく進めるために大切なこと
相続紛争は、親族間の感情的対立が起こりやすいことや、そもそも遺産の全容を把握することが困難であることなどの原因により、長期化することが多いと言われています。
遺産分割協議が長期化しないように、また円満に協議を成立させるためには様々な事項に注意する必要があります。
(1) 遺産の範囲について共通認識を得ること
遺産分割においては、協議を行う前提として「遺産の範囲について、全相続人の認識を一致させること」が極めて重要です。
遺産の範囲について全相続人の認識を一致させるには、主導的な相続人が、可及的速やかに遺産を調査し、遺産の目録を作成した上で、早期に全相続人に開示することが必要です。
ただし、単に遺産目録だけを開示しても、感情的な対立がある場合等には、「こんなに少ないはずはない、もっと遺産があったはずだ。」などとあらぬ疑いを生じることがあります。そのため、遺産の目録には、各財産の明細となる客観的な資料を添付することも肝要です。
場合によっては、疑いをもった別の相続人が自分でも調べてみると言い出すこともあり得ますが、そのような場合には可能な限り誠実に回答し、知り得る限りの情報を開示していることを理解し納得してもらうことが一般的には望まれます。
(2) 遺産の評価額について共通認識を得ること
遺産の範囲を確定できたら、それぞれの遺産の「評価額について、全相続人の認識を一致させること」が重要となります。
多くの場合、個々の遺産の客観的価値を算定せずに、各相続人間で遺産分割の話し合いをスムーズに進めることは困難です。特に、評価額の算定が問題になる財産には、(1)不動産、(2)非上場会社の株式等が挙げられます。
ア. 不動産
不動産については、公的基準(一般には固定資産税評価額や、路線価等)をもとに、相続人間で協議を行い、評価額について共通認識を得ることが必要です。また、公的基準のみでは合意が得られない場合には、不動産業者の簡易査定や、不動産鑑定士の正式な鑑定を依頼する場合もあります。
ただし、せっかく鑑定を行ったとしても、一部の相続人が鑑定結果に異議を唱える場合もあり得るでしょう。また、不動産鑑定士の鑑定には費用もかかりますので、後で費用の負担方法についてトラブルが派生しないようにしておくことも検討しなければなりません。
具体的には、鑑定を行う前に、全相続人から、(ⅰ)鑑定結果に異議を述べない旨の念書を取ったり、(ⅱ)鑑定に要した費用については法定相続割合に応じて各相続人が負担する旨の覚書を作成したりしておく等の対策をしておくことがトラブル防止のために有用です。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ 解決例 「事例3 不動産の評価額に折合いがつかなかったケース」
⇀ 解決例 「事例15 多数の不動産の取分けに難航したケース」
⇀ Q&A法律相談 換価分割
イ. 非上場会社の株式
非上場会社の株式には市場価格がないため、株式の評価額を算定することは容易ではありません。非上場会社の株式の評価方法としては、たとえば(ⅰ)純資産方式、(ⅱ)配当還元方式、(ⅲ)類似業種比準方式、(ⅳ)混合方式等が挙げられます。
このうちどの方法をとるか、またはその他の方法をとるかはケースバイケースであり、相応の知識や経験が必要となります。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ 解決例 「事例11 非上場会社の株の価値が問題となったケース」
(3) 強力なリーダーの必要性
相続紛争を話合いによって解決するには、強力なリーダーの存在が極めて重要です。
そもそもリーダーが主体的に遺産調査、遺産目録の作成及び開示を行い、話合いを主導しなければ、いつまでも協議は進みません。リーダー不在のまま長期間放置してしまったが故に、きっかけを掴めずにその後何年も分割協議の機を逸してしまったり、場合によっては互いに疑心暗鬼になったりして関係がこじれてしまうことが多々あります。
また、遺産についての共通認識を得ることができ、協議が一定の段階まで進んだ場合には、リーダーは遺産分割案を作成し、各相続人の意見に応じて修正案を作成していく等、緻密かつスピーディな対応が必要となります。
そのような強力なリーダーシップをとるには、相続全般や関連する分野に関する幅広い知識、経験が必須となります。相続人の中に十分な知識、経験を有する方がいない場合には、相続問題に強い弁護士への相談をおすすめします。
こちらもあわせてご覧ください。
⇀ 相続問題の専門知識 分割方法の決定と遺産分割協議のポイント
⇀ 解決例 「事例13 相続人が多数で意思統一が期待できなかったケース」
⇀ Q&A法律相談 換価分割
当事務所では、遺産分割事件に精通した弁護士が、クライアントのご要望に合わせた最適なアドバイスを提供した上で、遺産分割に関するトラブルを未然に防ぎ、円滑かつ迅速な解決をサポートし、遺産分割を的確に進めてまいりますので、お気軽にご相談ください。
相続問題の専門知識