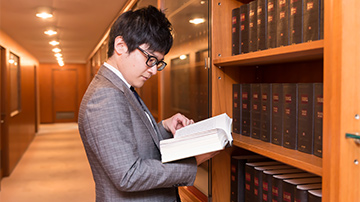相続一般
相続一般一覧
判例No. 1054
神戸地方裁判所尼崎支部 平成25年(ワ)第1048号 生命保険金請求事件
| 事件番号 | 神戸地方裁判所尼崎支部判決/平成25年(ワ)第1048号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成26年12月16日 |
| 判示事項 | 保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「法定相続人」と指定した場合、被保険者の死亡により具体化した保険金請求権は各相続人の固有財産となるから、(1)各相続人が相続放棄をしても、(2)各相続人が保険金請求権を放棄する旨の意思表示をしても、当該保険金請求権が他の相続人に帰属したり、被相続人の相続財産に帰属したりすることはないとされた事例。 |
判例No. 1063
最高裁判所第2小法廷 平成26年(受)第1312号、平成26年(受)第1313号 価額償還請求上告、同附帯上告事件
| 事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成26年(受)第1312号、平成26年(受)第1313号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成28年2月26日 |
| 判示事項 | 相続の開始後、認知によって相続人となった者が、他の相続人に対し遺産の価額を請求できるとする民法910条における遺産の価額算定の基準時。 民法910条に基づく価額の支払債務が履行遅滞となる時期。 |
| 判決要旨 | 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は、価額の支払を請求した時である。 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は、期限の定めのない債務であって、履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。 |
判例No. 1067
最高裁判所第1小法廷 平成28年(受)第579号 預金返還等請求事件
| 事件番号 | 最高裁判所第1小法廷判決/平成28年(受)第579号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成29年4月6日 |
| 判示事項 | 共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。 |
| 判決要旨 | 定期預金は、預入れ1口ごとに1個の預金契約が成立し、預金者は解約をしない限り払い戻しをすることができないのであり、契約上その分割払い戻しは制限されている。そして、この制限は、一定期間内には払い戻しをしないという条件とともに定期預金の利率が高いことの前提となっており、単なる特約ではなく定期預金債権の要素というべきである。そして、この理は、定期積金についても異ならない。したがって、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはない。 |
判例No. 1002
東京高等裁判所 平成15年(ツ)第56号 貸金請求事件
| 事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成15年(ツ)第56号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成15年9月18日 |
| 判示事項 | 被相続人の債権者から相続人に内容証明郵便が送付された場合において、その記載内容等からすれば、相続人に相続財産を認識させるには足りず、民法915条1項の熟慮期間がその時から進行するとはいえないとされた事例。 |
判例No. 1003
最高裁判所第3小法廷 平成15年(受)第1153号 相続権不存在確認請求事件
| 事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成15年(受)第1153号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成16年7月6日 |
| 判示事項 | 共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えは固有必要的共同訴訟か。 |
| 判決要旨 | 被相続人の遺産につき特定の共同相続人が相続人の地位を有するか否かの点は、遺産分割をすべき当事者の範囲、相続分及び遺留分の算定等の相続関係の処理における基本的な事項の前提となる事柄である。そして、共同相続人が、他の共同相続人に対し、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、当該他の共同相続人に相続欠格事由があるか否か等を審理判断し、遺産分割前の共有関係にある当該遺産につきその者が相続人の地位を有するか否かを既判力をもって確定することにより、遺産分割審判の手続等における上記の点に関する紛議の発生を防止し、共同相続人間の紛争解決に資することを目的とするものである。このような上記訴えの趣旨、目的にかんがみると、上記訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するものというべきであり、いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。 |