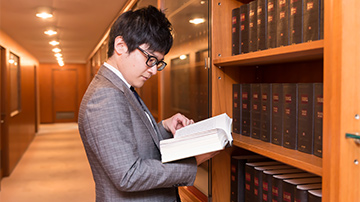遺産分割
遺産分割一覧
判例No. 1057
東京地方裁判所 平成25年(ワ)第8188号 不当利得返還等請求事件
| 事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成25年(ワ)第8188号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成27年4月22日 |
| 判示事項 | 原告である相続人が、遺産分割協議の当時、被相続人の死亡前後に引き出された多額の預貯金(4,330万円)や、遺産分割協議書に記載されていない財産(上場株式)の存在を知らなかったという場合において、原告である相続人は、遺産分割協議書には被相続人のほぼ全ての財産が記載されていると誤診していたものであるから、当該遺産分割協議は錯誤により無効であるとされた事例。 |
判例No. 1004
最高裁判所第2小法廷 平成16年(許)第11号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
| 事件番号 | 最高裁判所第2小法廷決定/平成16年(許)第11号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成16年10月29日 |
| 判示事項 | 被相続人が保険契約者及び被保険者であり、共同相続人の1人又は一部の者が保険金受取人となっている養老保険契約に基づく死亡保険金請求権が、民法903条の定める特別受益に当たるか。 |
| 判決要旨 | 被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではないというべきである。また、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない。したがって、上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらない。 もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。 |
判例No. 1059
札幌高等裁判所 平成27年(ラ)第6号 遺産分割及び寄与分を定める処分申立審判に対する抗告事件
| 事件番号 | 札幌高等裁判所決定/平成27年(ラ)第6号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成27年7月28日 |
| 判示事項 | 低額の給与で被相続人が経営する簡易郵便局の事業に従事したことが、被相続人の財産形成に対する特別の寄与に該当するとの相続人の主張に対し、相続人が得ていた給与は相応の金額であること、被相続人が当該相続人の食費・家賃等を支出していたこと等を理由として、特別の寄与には該当しないとされた事例。 |
判例No. 1005
最高裁判所第1小法廷 平成16年(受)第1222号 預託金返還請求事件
| 事件番号 | 最高裁判所第1小法廷判決/平成16年(受)第1222号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成17年9月8日 |
| 判示事項 | 共同相続した不動産から生ずる賃料債権の帰属と、後にされた遺産分割による影響の有無について。 |
| 判決要旨 | 相続開始後に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、後にされた遺産分割によって、当該賃料債権の帰属が影響を受けることはない。 |
判例No. 1061
大阪高等裁判所 平成27年(ラ)第908号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告事件
| 事件番号 | 大阪高等裁判所決定/平成27年(ラ)第908号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成27年10月6日 |
| 判示事項 | 相続人の一人がみかん農家である被相続人とともに農業に従事していたことが寄与分にあたるかどうかが争われた事例において、遺産である農地が荒廃せずみかん畑として維持できたことは当該相続人が農業に従事したことによるものであり、当該農地の価値の減少を防いだことが特別の寄与にあたるとして、当該農地の評価額の30%相当額が寄与分として認められた事例。 |